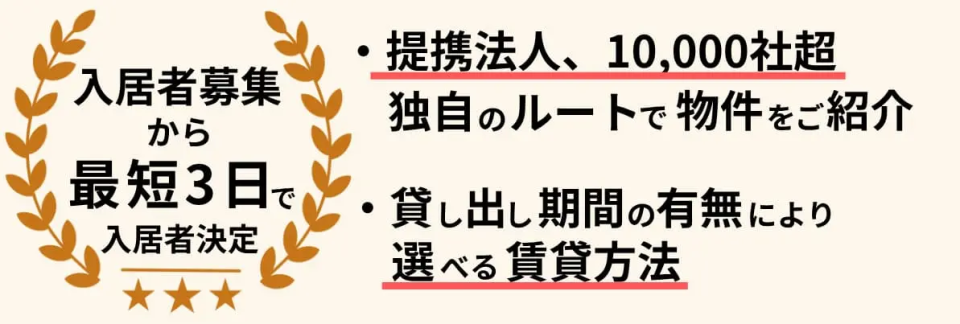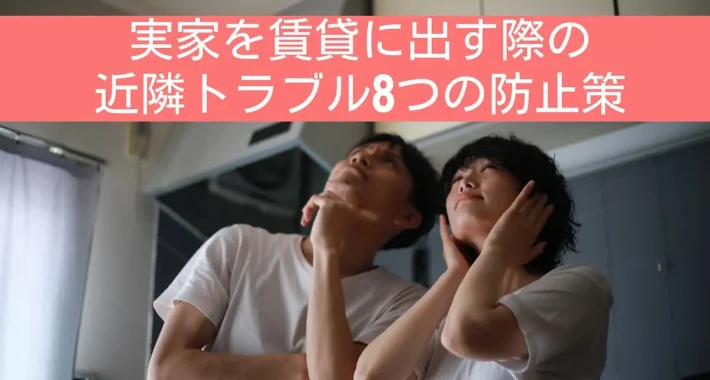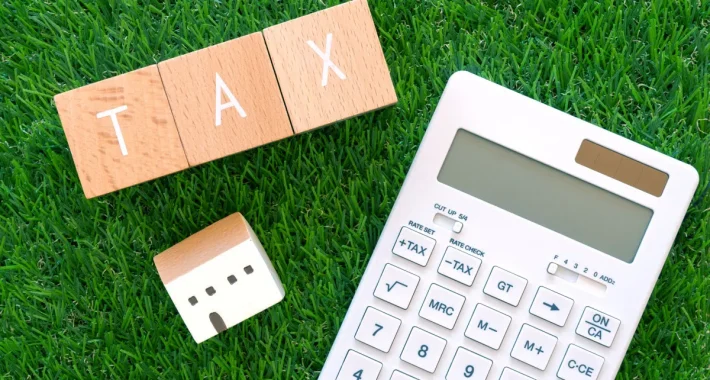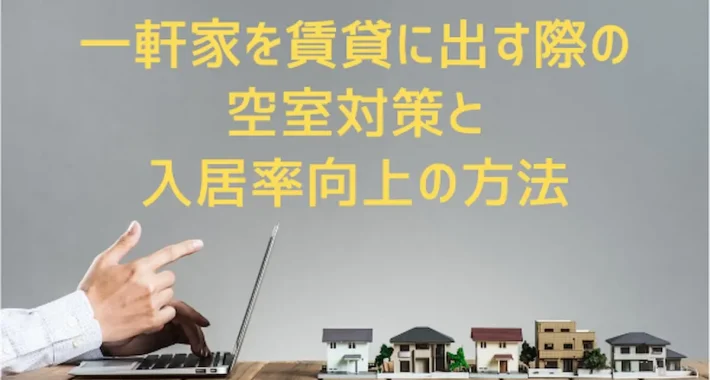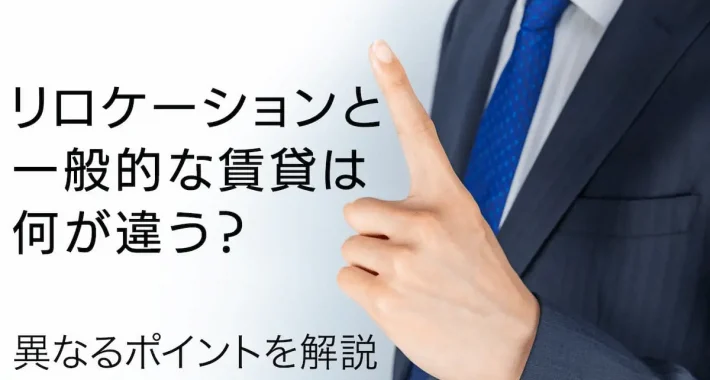家査定、依頼前の準備と注意点!成功する無料査定のポイント
これまで住んでいた自宅から引っ越すことになり、自宅を賃貸として活用する検討をした場合に、まず気になるのが「家賃」です。「賃貸経営なんてしたことがなく、家の査定なんて初めて」という方もいるでしょう。
この記事では、家の査定を依頼する前に準備しておくことや確認事項、査定依頼時の注意点、不動産会社に伝えておくこと、査定を成功につなげる攻略法について紹介します。
1. 家の査定前にしておく事前準備と確認する内容

家の査定を依頼する際は、なるべく不動産会社とのやり取りを減らし、スムーズに進めたいものです。ここでは、査定の事前準備として用意しておくもの、確認しておくことをご案内します。
1-1. 住宅ローン残高を確認
住宅ローン支払い中の家は、原則として貸すことはできません。
例外として、海外赴任や転勤などで一時的に引っ越し、帰任後に再入居を予定している場合などは、金融機関によって賃貸を認められる場合があります。
金融機関によって規約が異なるので、契約書を確認するか金融機関に直接確認しましょう。
それ以外の場合は、住宅ローンの残債を一括返済しなければいけません。一括返済が難しい場合はアパートローンなどに借り換える必要があります。
賃料を決める際にも住宅ローン残高は重要な情報になるので、家の査定前に確認しておきましょう。
1-2. 書類の有無を確認する
持ち家の賃料査定の前に準備しておく書類は、次の通りです。対応する不動産会社や求める査定の精度によっても異なる場合があります。当社「リロの留守宅管理」で必要な書類は建物の図面のみです。
- 建物の図面
- 付帯設備書
- 契約書(管理規約、使用細則)
- 登記簿謄本
- 重要事項説明書
- リフォーム時の書類(リフォーム履歴があれば)
1-3. 家の修繕履歴やリフォーム・リノベーション実績の確認
家の査定前にこれまでの修繕履歴などをまとめておくとよいでしょう。
シロアリ対策や外壁塗装、耐震性能の強化などの維持保全は建物の価値を維持、場合によっては建物の寿命を延ばします。
さらに、リフォーム・リノベーションによって、建物の価値が上昇するため、これらは査定額を上げられることが期待できるだけでなく、入居者が早く決まりやすい重要なポイントになります。
広告にも「20●●年リフォーム済み」などと掲載できます。貸し出す際、借主は色々な家と比較するので、大きなアピールポイントとなるでしょう。
2. 家の査定は無料-無料査定の攻略方法
家を貸す場合は、最初に不動産会社に賃料査定を依頼します。
査定には机上査定と訪問査定があり、どちらも無料です。営業担当者がご自宅を訪問査定する際も出張料のようなものは発生しません。売却の場合は、稀に有料になる場合もありますが、 家を貸すときの査定はどの不動産会社でも完全無料です。
いくつか理由がありますが、将来的な顧客になってもらうための営業活動の一環で賃貸管理の委託契約が出来れば管理手数料を得ることができるためです。
2-1. 机上査定と訪問査定を受ける意味
先述したように査定には机上査定と訪問査定があります。それぞれの内容は次の通りです。
机上査定
不動産会社のホームページや電話から物件の情報(築年数、場所、間取り)を入力し情報送信後、それをもとに概算賃料を提示します。当社の「リロの留守宅管理」は、翌営業日を目途にメールか電話などで机上査定の結果をお伝えしています。その際、簡単な説明をする場合もあり、電話でご連絡することが多いです。
訪問査定
実際に物件にお伺いして家の状態や周辺地域を確認しながら詳細な賃料を算定するために行われます。 訪問をしないと分からない事も多いので、最終的な賃料を算出するためには訪問査定が必要になります。
2-2. 査定の依頼方法
無料査定の依頼方法は3つあります。
- 賃貸管理会社に電話で依頼する
- 賃貸管理会社のホームページから依頼する
- 一括査定サイトから依頼する
賃貸管理会社の選び方は、賃貸管理実績が豊富であること、集客方法が複数あり質の良い客付けが出来そうな会社を選びましょう。
一括査定サイトというのは、複数の賃貸管理会社から同時に賃料査定が得られるサービスです。入力に掛かる時間は各社によりますが、1~3分で終わると思われ簡単な質問が多いです。
インターネットの入力が手間に感じる場合は、直接賃貸管理会社に電話しましょう。「リロの留守宅管理」では査定専用窓口があります。年末年始以外は営業していますが、営業時間(9:30~17:30)があるのでご注意ください。
2-3. 家査定の攻略方法
家を査定するときは「一括査定サイト」「賃貸管理会社のホームページ」から査定する方法が大半です。
一括査定サイトは、1度で複数の管理会社に賃料査定の依頼をすることができます。 その場で査定結果が出ることはなく、後日担当者から連絡が入るのが大半です。
一括査定サイトは便利なサービスではありますが、入力した物件情報などが各業者に一斉に流れます。どの管理会社が連絡してくるかは一括査定サイトによって異なり、連絡があるまで申込した管理会社が分からない場合もあるので、期待していた管理会社から連絡がないこともあります。
また、一括査定サイトで申し込みができた場合でも、 管理会社によって対応できる物件が異なり、一旦受け付けされても賃料査定を受けられないこともあります。対応できない物件の場合は、査定結果は得られず、手間だけがかかることになります。一括査定サイトは、各社の条件が異なっていても共通した入力フォームを使っているため、このような事象が起こります。
一方、管理会社のホームページから査定する場合は、管理会社のホームページで事前に対応エリアなどを確認できたり、申込フォームの入力が制御されたりすることで、対応の物件であるかどうかを知ることができます。
査定の攻略方法は、 自分で管理会社をインターネットから検索して各社の特徴や実績を把握し、査定を依頼することです。少し手間は掛かりますが、契約する上でもパンフレットだけを参考にせず、インターネットで改めてホームページや評判を検索すると思います。
最終的にホームページを確認するなら、最初から自分で賃貸管理会社を検索して、納得してから査定を依頼することが望ましいといえます。
いずれの場合でも、 査定では複数の管理会社に依頼し、各社の違いや査定額の根拠を聞くと良いでしょう。
これらは、持ち家を購入する場合でも気になるポイントでしょう。査定のポイントは自分が選ぶ立場であったらどうか、という視点も入れて考えてみてください。
関連記事
家の貸し出し方法|賃貸と賃貸併用住宅

3. 家の査定時の不動産会社の注意点
次に、持ち家の査定をする際に注意することをご案内します。不動産会社の選定をする際のポイントとなりますので、詳しく解説していきます。
3-1. 複数の不動産会社に依頼する
査定を行う際は1社のみでなく、複数社に依頼しましょう。
査定を行う際は、過去の成約実績や現在募集中の物件などのデータから類似物件を抽出し、類似物件の賃料をベースとして査定対象となる持ち家に合わせて、 設備や周辺環境の違いに合わせて調整を行いますが、どの程度査定額の調整を行うかは、担当者や会社の経験によって異なるためです。また、ファミリー向けの物件や店舗付き物件など、市場全体において割合が少ないタイプの物件の場合は、取り扱い実績が豊富な不動産会社に直接依頼しましょう。
3-2. 高すぎる査定額を提示する不動産会社には注意が必要
他社と比較して高額な査定額を提示する不動産会社には、注意が必要です。賃料査定は、管理会社にとっては営業行為の一環であることから、管理を受託することが目的で、あえて高めの賃料を提示してくる会社もあります。
実際に借り手がつくかどうかは、入居者を募集してみなければわかりません。。。また、査定よりも高い価格で募集する場合も、相場より高いためになかなか入居者が見つからず、空室期間が長引いてしまうことがあります。
3-3. 持ち家の査定額の根拠をしっかり確認する
前項の通り、管理を受託することが目的であえて高めの賃料を提示してくる会社もあります。
そのような査定結果に惑わされないためには、査定額の根拠を確認し、提示された査定額は「確実に入居者を見つけられる査定額なのか」「入居者が決まる家賃の上限額なのか」を把握しましょう。信頼できる管理会社であるか、契約するか判断するための材料にもなるでしょう。
3-4. 成約価格の相場を確認する
SUUMOなどのポータルサイトに掲載されている物件は、まだ入居者が決まっていない物件であり、あくまでも入居者募集中の価格で、この金額が家賃になるとは限りません。
そのため、査定の際に管理会社に家賃の相場を確認し、予定している募集価格と開きがないか「類似の物件ではどれくらいの賃料で貸し出せていますか?」などと確認してみましょう。そうすることで査定額が妥当であるかが分かり、その管理会社を信用できるかのポイントにもなるでしょう。
関連記事
信頼できる不動産会社の選び方とポイント、家を貸すときは管理会社が重要!

4. 家の無料査定を成功させるポイント
4-1. 希望や条件、相談事項を事前に伝える
査定依頼の際、希望や条件、相談事項などを事前に伝えましょう。
希望や条件の主な例は以下のようなものが考えられます。
- 貸し出し希望時期
- 転勤などの一時的な賃貸である場合、そのことや再入居の希望があるか
- あらかじめ期間を限定して貸し出したい場合は、貸し出し期間の目安
- 希望賃料
- ぞんざいに扱って欲しくないので、入居者の質に気を付けて欲しい
- ペットやたばこは禁止
投資目的なら賃料の下限があるかと思います。必ずしも希望賃料で貸し出せるとは限りませんが、希望や現在の状況は伝えるべきでしょう。
転勤などの場合で一時的に貸し出す場合は契約方法が変わることが考えられます。また、貸し出せる期間によっても査定額が変わるので事前に伝えておきましょう。
入居者の質であれば、転勤が多い法人(大手企業)との提携が多い管理会社を選ぶと良いでしょう。社宅として契約できる可能性があります。事前に確認しましょう。
4-2. アピールできるところを探す
アピールできることが多いのは査定を成功させるポイントの一つです。安全性が高く、設備が充実している物件は賃貸管理会社も勧めやすく、以下のような点が挙げられます。
- シロアリ対策
- 外壁塗装
- 耐震性能の強化
- 最新の設備(エアコンを付け替えたばかりで省エネ家電、浴室乾燥機、食洗器など)
- 商業施設や病院が近くにあり生活しやすい
- 電車など複数路線が乗り入れており便利
4-3. 不具合や瑕疵(かし)はきちんと伝える
マイナスな点は隠さずに伝えましょう。説明せずに後から指摘をされれば「契約不適合責任」として損害賠償請求などにも繋がります。
主な瑕疵として以下のようなものが挙げられます。
- 雨漏り、ひび割れ、床の傾き
- エアコンが故障している
- シロアリなどの建物の腐食
- 騒音、日照障害、反社組織が近くにある
- 過去に刑事事件が発生した事故物件
マイナスな箇所は全て伝え、どのような方法であれば不具合が解消できるか管理会社と相談しましょう。マイナス箇所が1つでも減らせれば、査定が成功に繋がります。
5. まとめ
ここまで、家の査定について攻略する方法や成功するポイントをお伝えしました。
査定の前に、家を購入した時の書類や修繕履歴、リフォーム・リノベーション歴についても、あらかじめ準備しておくとよいでしょう。
また、住宅ローンがある場合は金融機関に確認が必要です。
査定を成功させるポイントは一括査定よりも自分で管理会社を調べて特徴などを理解した上で複数の会社に依頼すること、同時に賃料相場を確認し希望の条件など物件のセールスポイントを整理しておき、しっかり伝えることです。あわせて、物件に不具合がある場合は事前に全て伝えましょう。