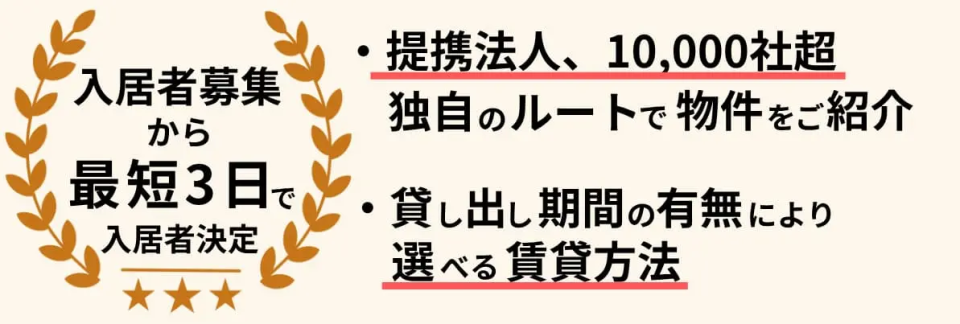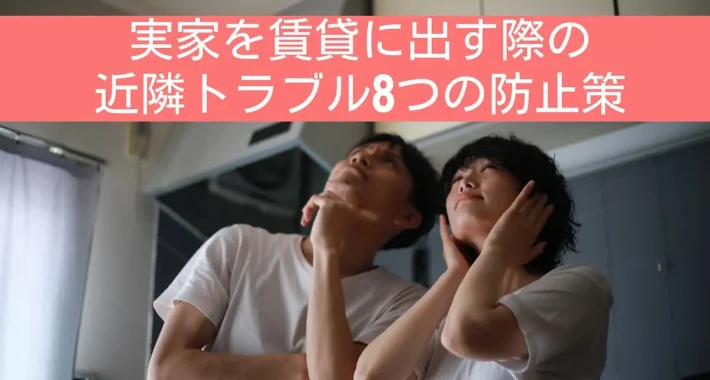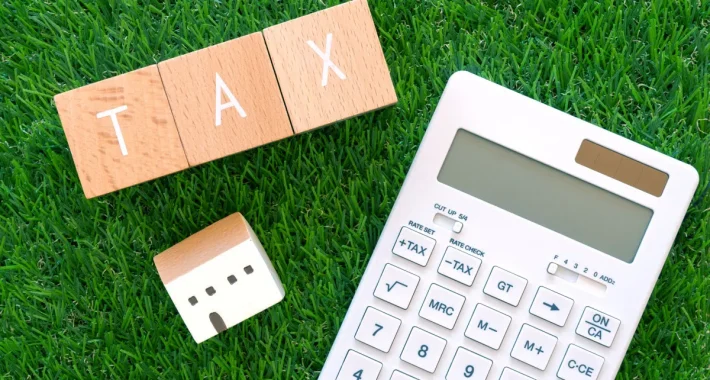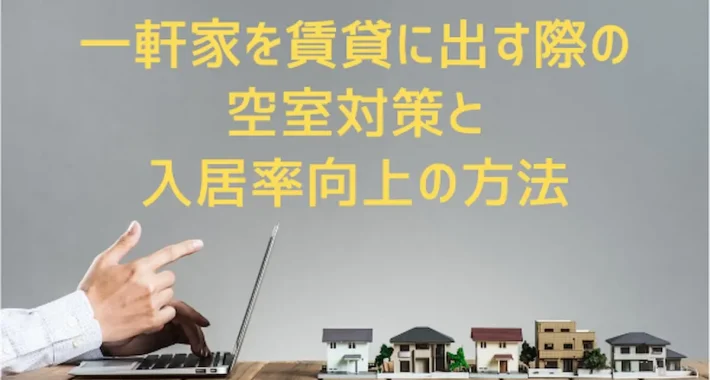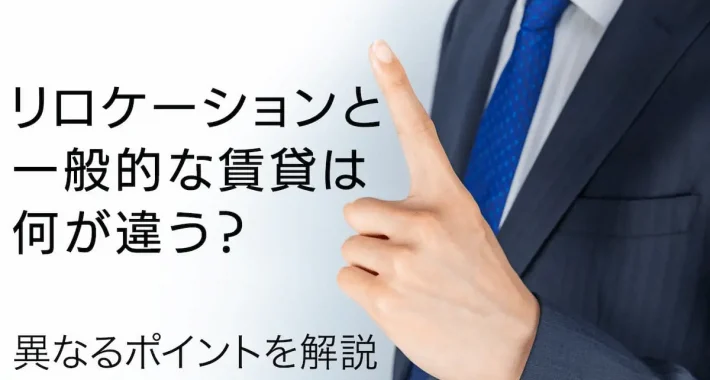家やマンションを貸し出して家賃収入を得ている場合、原則として確定申告が必要ですが、不要なケースもあります。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、青色申告では申告方法や記帳方法の違いによって受けられるメリットが増えます。
今回は、確定申告の目的や方法、確定申告が必要なケースとともにそれぞれのケースに適した確定申告の方法について解説します。
1. 家賃収入があると確定申告が必要
持ち家を賃貸に出して家賃収入を得ることは「不動産業」に含まれ、家賃収入から必要経費を控除した利益を「不動産所得」と呼びます。
給与所得者は、不動産所得が年間20万円を超える(通年で家賃収入がある場合は、月の不動産所得が16,667円以上)なら確定申告をしなければなりません。給与所得者以外は、不動産所得を含めた「所得」が基礎控除額の95万円を超える場合、確定申告が必要です。
給与所得のみの会社員の方は給与天引きで源泉徴収され、会社の年末調整で納税や還付の手続きが完結することがほとんどですが、 不動産所得を得た場合は自身での確定申告が必要です。
確定申告の際には、分譲マンションを貸すために必要な支出について、家賃収入から必要経費として控除することができます。経費にできるものの一例を紹介します。
・固定資産税および都市計画税
・管理費
・賃貸管理手数料
・修繕費
・住宅ローンの利子
など
関連記事
持ち家を賃貸に出したときの確定申告や税金、計算方法と申告方法を解説

1-1. 確定申告とは
確定申告とは、1年間でどのくらいの所得を得たのかを算出し、所得にかかる税金を計算して所得と納税額を申告し、納税するという、一連の手続きのことを言います。
1月1日から12月31日までの1年間分の所得について、翌年2月16日から3月15日までに税務署に必要書類を提出の上、所得税額を納付します。
1-2. 確定申告の義務がある人
収入から、収入を得るためにかかった経費を差し引き、さらに所得控除を差し引いた金額を課税所得といい、課税所得がある場合は確定申告が必要です。
ただし、給与所得や退職所得の場合、会社が源泉徴収と年末調整を行うため、原則として確定申告を行う必要はありません。これらを除いた他の所得が合計で20万円以上あった場合は、それらの所得についての確定申告が必要となります。これには家賃収入による不動産所得も含まれます。
確定申告をしなければならない人が確定申告を行わなかった場合には、追加の支払いを課されるなどの罰則があります。
参考:「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」[国税庁]
1-3. 確定申告が不要なケース
前述の通り、給与所得があるときには、不動産所得を含めた他の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
また、赤字になるなどして課税対象となる所得がない場合は、所得税がかからないので確定申告は不要です。
さらに所得があっても、所得税額を計算する際には「配偶者控除」や「扶養控除」等の所得控除があり、一定の要件に当てはまる場合は所得の合計金額から所得控除額を差し引くことができます。所得金額から所得控除額を差し引いた結果、所得額が課税対象額以下となれば、このときも確定申告は不要になります。
参考:「No.1100 所得控除のあらまし」[国税庁]
1-4. 義務ではなくても確定申告をした方が良いケース
「給与所得があって、不動産所得もある」というように複数種類の所得がある場合には「確定申告により節税できる」ケースがあります。それは、「不動産所得」「事業所得」「譲渡所得」「山林所得」があるものの、経費の方が大きくなるなどして、計算上で損失が発生し、赤字となっている場合です。このような場合に確定申告を行うと、黒字となっている他の所得から損失分を控除する損益通算という方法で、所得税額を抑えることができます。
参考:「No.2250 損益通算」[国税庁]
2. 不動産所得の計算方法と経費計上できる項目

ここまで、確定申告の有無に関わる「不動産所得」は「収入から経費等を引いた額で、大まかに言えば儲け」です。しかし収支は物件によって異なり、具体的な所得額がどれくらいかは、その内訳を見なければ分かりません。実際にどのような計算をしなければならないのか、家賃収入以外の収入に含めなければならない項目や経費として計上できる費用など、具体的に挙げて解説しましょう。
2-1. 不動産所得とは
賃貸経営で得られる不動産所得とは、賃料を含めた賃貸経営で得られる収入の総額から、賃貸経営のためにかかった費用(経費)を差し引いた額です。
所得金額=総収入金額-必要経費
2-2. 賃貸経営時の総収入金額に含まれるもの
賃貸経営では次のようなものが総収入金額に含まれます。
・物件を貸し出すことによって得られる賃料収入
・賃料とは別に共益費や管理費といった名目で、物件を借りること以外の料金として得られる収入
・礼金、更新料などの収入
・敷金や保証金などとして受け取った金額のうち、入居者に返還する必要がない部分
2-3. 必要経費として課税対象から差し引くことができる費用
必要経費として認められるものは、賃貸経営のためにかかる費用です。壊れた設備を直すための費用や、税金、保険料といったものがあります。具体的に必要経費として認められるものは、次のような費用です。
| 固定資産税・都市計画税、不動産取得税、登録免許税、印紙税等の税金 | 土地や建物を所有していることで毎年納付が必要となる税金や土地や不動産を取得した時にかかる税金は、必要経費として計上することができます。 |
|---|---|
| 火災保険、地震保険等の保険料 | 建物にかかる損害保険料も必要経費として認められます。 |
| 借入金の利子 | 土地や建物を取得する際に借り入れたことによって生じる借入金の利子についても必要経費に計上できます。ただし、不動産所得が赤字となっており、損益通算を行う場合は土地にかかる借入金の利子分を除外しなければなりません。 |
| 広告宣伝料、仲介手数料、管理料等 | 入居者募集にかかる費用や不動産会社への仲介手数料、物件管理を依頼している管理会社に支払う管理料なども必要経費として認められます。 |
| 修繕費、原状回復費用 | 貸し出す建物の修繕にかかった費用や設備の修繕にかかった費用も必要経費として認められます。 |
| 減価償却費 | 建物は時間の経過とともにその価値が低下します。減価償却費とは建物の取得価格を耐用年数に応じて、各年に配分した金額です。減価償却費も必要経費として計上できます。 |
| 税理士報酬等 | 確定申告を税理士に依頼した場合の税理士報酬等も必要経費として認められます。 |
このように、賃貸に関わる総収入額と必要経費がそれぞれいくらかをまとめて、総収入額から必要経費を差し引いた残りが不動産所得となります。加えて前述した所得控除等を踏まえることで、取得した家賃収入についての確定申告が必要かどうかを判断できます。
3. 家賃収入の確定申告の方法

確定申告の方法には「白色申告」「青色申告」の2種類があります。また、記帳方法や申告時の提出書類の様式も、複数あります。最適な確定申告方法は、賃貸経営を行う状況などによって異なります。
ここでは、確定申告書の作成方法や申告に必要な書類、申告方法などについて説明していきます。
3-1. 控除額が変わる、確定申告の2つの種類(白色申告・青色申告)と2つの記帳方法
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2つの種類があり、それぞれ次のような特徴があります。
白色申告とは
白色申告は、事前の届出が不要で、青色申告に比べて手続きが簡単な申告方法です。白色申告で提出すべき書類は「確定申告書B」と「収支内訳書」の2つであり、記帳も簡易的な単式簿記という方法で問題ありません。
提出書類が少なく、簡易的な手続きで申告ができる点が白色申告のメリットですが、特別控除等が適用されないため、青色申告のような節税効果はありません。
青色申告とは
青色申告ができるのは不動産所得、事業所得、山林所得の3ついずれかの所得がある人です。事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に届け出ていなければ、青色申告を行うことはできません。
「確定申告書B」に加えて「青色申告決算書」の提出が必要になるほか、複式簿記での記帳が原則として求められます。青色申告では、所得から最大65万円の控除を受けられる青色申告特別控除が適用され、所得の中で赤字が生じた場合に、その赤字分を3年間まで繰り越しすることができるといったメリットがあります。
保存すべき帳簿の数も多くなり申告に手間がかかるものの、青色申告では課税額を抑えやすいメリットがあります。
単式簿記とは
1回の取引に対して、1つの勘定科目に絞って記載する方法です。いくらお金が入り、いくら支払ったのかといったお金の増減に注目した記帳を行います。
複式簿記とは
1回の取引に対して、複数の勘定科目で記載する方法です。お金の増減に加えて、資産や負債の増減についても記帳を行います。取引を発生の原因と結果に分けて記録することにより取引の結果、現金残高や収支がどのように変わったのかを把握することができますが、単式簿記に比べて複雑な記帳方法となります。
3-2. 不動産所得は事業的な規模かどうかで特別控除額が変わる
不動産所得の場合、青色申告特別控除額は事業的な規模で賃貸経営を行っているかどうかで変わります。マンションやアパートを10室以上貸しているか、または独立した家屋を5棟以上貸しているかなどが判断基準の1つとなっています。事業的な規模で家賃収入を得ている場合は、青色申告で最大65万円の控除を受けることが可能です。
マンション1室を貸している場合や転勤の間だけ自宅を貸しているケースなど、事業的な規模に該当しない場合であると、65万円の控除を受けることは難しいですが、その場合でも10万円の控除は受けられます。
| 青色申告(最大65万円控除) | 青色申告(10万円控除) | |
|---|---|---|
| 対象となる経営規模等 | 10室以上の部屋or5棟以上の貸家賃貸経営の規模がいずれかに相当するなどして事業的な規模として認められる |
事業的な規模として認められない場合 事業的な規模であっても最大65万円の青色申告特別控除の要件に該当しない場合 |
| 家族や親族への給与 | 必要経費になる | 必要経費にならない |
| 青色申告特別控除 | 最大65万円 | 10万円 |
| 提出書類 | 確定申告書B 青色申告決算書(損益計算書・賃借対照表) |
確定申告書B 青色申告決算書(損益計算書) |
| 記帳方法 | 複式簿記 | 単式簿記 |
3-3. 確定申告書の作成方法
確定申告書の作成方法には次の4つの方法があります。
国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用する
国税庁のウェブサイトには、確定申告書を作成できる「確定申告書等作成コーナー」が用意されています。画面の案内にしたがって入力し、申告書や決算書などを作成することが可能です。
確定申告書作成コーナーはこちらです。
確定申告用のソフトを利用する
確定申告用のソフトでは、必要事項を入力していくだけで帳簿や確定申告書が簡単に作成できるようになっています。簿記の知識が無くても手軽に入力できるようになっているものもあり、計算も自動で行われるため手間がかからずに便利です。
手書きで作成する
確定申告書は、手書きで作成することも可能です。確定申告書は最寄りの税務署の窓口で配布しているほか、国税庁のホームページなどからダウンロードすることができます。書き方等に不安がある場合は税務署の窓口で質問できるほか、確定申告の時期には確定申告相談会場を設置している場合もあるため、相談しながら作成することも可能です。
税理士に依頼する
税理士に依頼し、確定申告書を作成してもらうことも可能です。どの範囲までを依頼するかによって金額は異なりますが、税理士に確定申告を依頼する場合には報酬を支払う必要があります。
3-4. 確定申告の提出書類
家賃収入に関する確定申告では、次のようなものが必要となります。
確定申告書B(大一表、第二表)
家賃収入に関する確定申告では、不動産所得のある人が使用できる確定申告書Bを使用します。白色申告をする人も青色申告をする人も、必ず提出が必要になる書類です。
収支内訳書(白色申告をする人のみ)
収支内訳書は確定申告書を作成するために、1年間の家賃や礼金等による収入、固定資産税・修繕費・仲介手数料・管理料・減価償却費などの必要経費を記載するものです。収支内訳書は複数種類ありますが、家賃収入がある場合は「不動産所得用様式」を使用します。
青色申告決算書(青色申告をする人のみ)
青色申告決算書は、1年間の利益を表す「損益計算書」と資産や保有資産や負債などの状況を表す「貸借対照表」の2つからなる書類です。
青色申告決算書においても、収支内訳書と同様に、家賃収入がある場合には「不動産所得用様式」を使用します。
ただし、事業所得と不動産所得の合計所得金額が300万円以下の人で、事前に「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出している場合には、「現金主義様式」を使用でき、「貸借対照表」の提出が不要になります。
現金主義とは、年末までに現実に金銭等を受領した金額を収入として扱う考え方です。前述した条件を満たしている人であれば、現金紙器簡易簿記というより簡便な方法で記帳しても構いません。現金主義を用いた場合は、最高55万円の特別控除が適用される事業規模であっても、最高10万円の青色申告特別控除のみの適用となります。
参考:「確定申告に関する手引き等」[国税庁]
3-5. 確定申告書の提出方法
確定申告書の提出方法には、次の3つの方法があります。青色申告の場合、記帳方式だけでなく、提出方法によっても特別控除額が変わるため注意が必要です。
e-Taxによる提出
e-Taxとは国税電子申告・納税システムのことで、インターネットを利用して確定申告書の提出ができるシステムです。確定申告書作成コーナーや確定申告ソフト等で作成したデータを用いて申告手続きができます。
e-Taxを利用するには、マイナンバーまたは税務署により発行されるID・パスワードによって利用者識別番号(アカウント)を取得する必要があります。ID・パスワードの発行は税務署での本人確認が必要です。
e-Taxを利用して青色申告を行う場合、最高65万円の青色申告特別控除を受けられるというメリットがあります。65万円の特別控除の適用を受けるためには、複式簿記で記帳するなどの他の条件を満たすことと併せて、e-Taxによって確定申告を行うか、後述する電子帳簿保存を行った上での確定申告を行う必要があります。
税務署に持参する
作成した書類を管轄の税務署に持参して窓口で提出することも可能です。混雑する可能性がありますが、不明点があった場合に税務署の職員に直接相談しながら提出できる点がメリットです。税務署へ持参した場合に、青色申告特別控除の限度額である65万円の特別控除を受けるためには、電子帳簿保存法の申請承認書を事前に税務署に提出し、市販の会計ソフトを用いるなどして電子帳簿保存を行い、他の条件について問題なく満たしていることが必要です。電子帳簿保存がない場合は、青色申告特別控除額は55万円までとなります。
税務署に郵送する
提出期限日の消印が有効となります。税務署に書類を持参した場合と同様に、電子帳簿の保存がない場合は青色申告特別控除額は55万円までとなります。
持参や提出が必要な書類については、国税庁の「申告書に添付・提示する書類」のページでご確認ください。
4. 確定申告をしなかった場合のリスク
所得が発生したら確定申告によって自ら所得を申告し、納税を行わなければなりません。必要な申告と納税を怠った場合、次のような罰則が科せられます。
4-1. 無申告加算税
期限内に確定申告をしなかった場合、本来の課税額に加えて、無申告加算税が課税されます。追加で課される金額は元の納税額によって変わります。納税額が50万円までは15%を掛けた額が上乗せとなり、50万円を超えている場合には、50万円を超えた分に対して20%を掛けた額が上乗せされます。
なお、期限内に申告していなかった場合でも、税務署からの調査を受ける前に自分から申告をすれば罰則は軽くなります。その場合追加されるのは元の納税額の5%です。
また、申告期限を過ぎてから1か月以内に自ら申告をしたときには、無申告加算税を無し(不適用)にしてもらえることもあります。ただし、不適用が認められるのは、期限内に申告をする意思があったと認められた場合です。
参考:「No.2024 確定申告を忘れたとき」[国税庁]
4-2. 延滞税
期限内に税金を納めなかった場合、納付期限の日から納付するまで1日ごとに延滞税が加算されます。2か月経過までは元の納税額に対して最大で年7.3%ですが、2か月経過後は最大で年14.6%と高くなります。
参考:「延滞税の計算方法」[国税庁]
「無申告加算税」と「延滞税」を合わせると多額の納税が課せられることになります。これらの罰則を受けるリスクを避けるためにも確定申告は定めに従い、期日までにしっかりと行うべきでしょう。
もし何かしらの事情で期日を過ぎてしまった場合には、まずは所轄税務署を調べて相談してみるなど、課税額がさらに大きくならないように対応を急ぎましょう。
5. まとめ
家賃収入で得られる利益は不動産所得に該当し、基本的には確定申告が必要となります。しかしながら、家賃収入があっても確定申告が不要なケースもあります。課税対象となる所得は総収入から必要経費を引いたものであり、所得額から要件に該当する所得控除を差し引いた残額があれば、確定申告が必要です。確定申告が不要であった場合でも、損益通算を行うことで他の所得にかかる税額を抑えられる可能性もあります。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、書類の提出方法にもいくつかの方法があります。申告方法や書類の提出方法によって課される所得税額は変わり、事業的な規模であると認められる場合にe-Taxを使用して青色申告を行うと、青色申告特別控除の最大額65万円の控除を適用できます。一方、事業的な規模に該当しない場合は青色申告を行っても65万円の控除は受けられず、現金主義用様式(単式簿記)の申告で十分な可能性があります。
確定申告が必要であるにも関わらず確定申告を行わなかった場合は、罰則によって多額の税金を納めなければならなくなるリスクもあります。
まずは所得額を計算し、確定申告が必要かどうかを確認するようにしましょう。