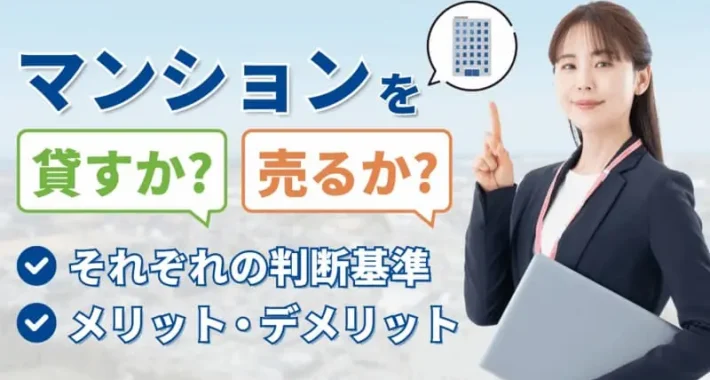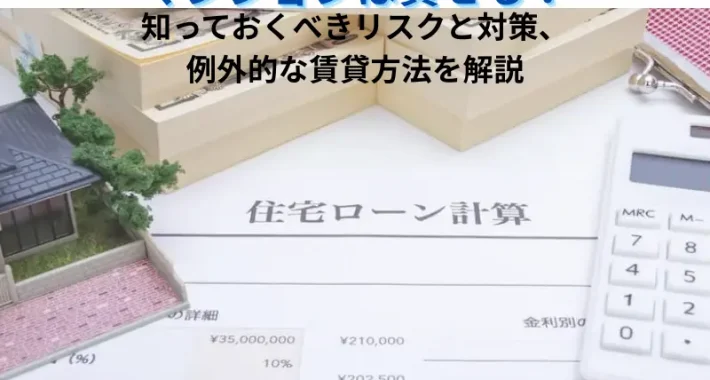近年はマンションに住んでいる高齢者も多いことから、相続で親のマンションを引き継ぐケースが増えてきました。
親からマンションを相続した人の中には、自分が住む予定はなく、どう扱うべきか悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
相続したマンションの扱いに迷ったら、まず賃料査定を依頼するのが第一歩です。
賃料査定を行えば貸せるかどうか、また貸すべきか売るべきかの判断基準が見えてきます。
査定の結果から、貸すべきか、売るべきかの選択肢が見えてくるため、賃料査定は相続したマンションの扱いを決める重要な第一歩です。
この記事では、「相続したマンションを賃貸に出す」というテーマについて、メリット・デメリット、手順、注意点を解説します。
目次
1.相続したマンションが賃貸に向いている理由

最初に相続したマンションが賃貸に適している理由について解説します。
1-1.戸建てに比べると立地の良い物件が多い
マンションは戸建てよりも立地に恵まれているため、賃貸に出しやすい物件が多いです。
高層建築物であるマンションは、駅近など便利なエリアに建てられることが多く、賃貸需要が集まりやすいのです。
賃貸需要は立地の良い場所に偏在するため、売ることはできても貸すことができない物件は多く存在します。
高層建築物であるマンションは、必然的に都市部の利便性の高い場所に建っており、賃貸に適した物件が多いです。

竹内英二【資格】不動産鑑定士、賃貸不動産経営管理士
【ワンポイントアドバイス】
マンションは戸建てに比べると賃貸面積が小さいため、家賃も抑えやすいです。マンションは家賃を借主が許容できる範囲に収めやすいことから、戸建てに比べると借主を見つけやすくなります。
1-2.住宅ローンを完済しているケースが多い
相続したマンションは多くが住宅ローン完済済みのため、安心して賃貸に出せます。
住宅ローンが残っている物件は契約上貸せませんが、完済していれば契約違反の心配なく運用できます。
住宅ローンが返済中の物件を貸すと、マイホームではなく賃貸物件を購入したものとみなされ、銀行との間の契約で契約違反となってしまいます。
しかしながら、親から相続したマンションであれば、住宅ローンは完済していることが一般的です。
住宅ローンが完済していれば、銀行との間の金銭消費貸借契約は終了しています。
そのため、住宅ローンを完済しているマンションは、契約違反を気にせず貸すことができるのです。
1-3.大きな投資を伴わないので圧倒的にリスクが低い
親から相続したマンションは、投資をせずに得られたマンションです。
借入金も発生しないことから、一般的な不動産投資と比べると賃貸事業のリスクが圧倒的に低くなります。
仮に借主が見つからず、長期間の空室が続いたとしても、大きな痛手はありません。
1-4.分譲仕様で競争力がある
親が住んでいたマンションは、分譲マンションであることが通常です。
分譲マンションは賃貸マンションと比べると、仕様が優れており、市場における競争力が高くなります。
例えば、防音性や内装の仕上げ材、キッチンの機能、共用部の設備等の仕様は、賃貸マンションよりも分譲マンションの方が優れていることが一般的です。
分譲マンションは住み心地の良い物件が多いため、入居者に長く借りてもらえる可能性があります。
1-5.大規模修繕を管理組合に任せられる
分譲マンションは、大規模修繕を管理組合に任せられる点も貸しやすい点です。
アパートや一棟賃貸マンションでは、大規模修繕は貸主が資金を計画的に貯蓄し、自ら実施していかなければなりません。
相続人は親が運用していた築年数の古い物件を引き継いだ際、大規模修繕費用が貯まっておらず、大規模修繕に対応できないことも多いです。
分譲マンションの所有者は修繕積立金を払っておけば大規模修繕は管理組合に任せることができます。
物件を引き継いだ際に相続人に貯蓄がなくても大規模修繕に対応することができ、長期的に貸しやすいといえます。
2.相続したマンションを賃貸に出すメリット
この章では、相続したマンションを賃貸に出すメリットについて解説します。
2-1.安定した家賃収入を得られる
相続したマンションを賃貸に出すメリットは、継続的な不労所得が得られるという点です。
家賃収入は見通しの立てやすい固定収入であるため、生活を下支えする年金のような役割も果たしてくれます。
家賃という余剰収入が加われば、海外旅行に行ったり、ぜいたく品を購入したりすることも期待できます。

竹内英二【資格】不動産鑑定士、賃貸不動産経営管理士
【ワンポイントアドバイス】
賃貸に出した物件は、収益物件としていつでも売ることは可能です。売却すればそれっきりですが、賃貸を選択すれば将来売却もできるという選択肢が残っています。
実際にどのくらいの家賃収入が期待できるのかは、立地や築年数によって大きく異なります。まずは査定で相場を知ることが、判断の第一歩です。
2-2.入居者によって管理してもらうことができる
空き家は、建物の価値を維持するために一定の管理が必要です。
具体的には、定期的な換気や排水溝に水を流す通水が必要となります。
通水が必要な理由は、排水管には下水からの臭いを食い止める封水が溜まっており、封水が蒸発しきると部屋の中に汚臭が充満してしまうからです。
賃貸に出さず、空き家のまま放置すれば、所有者が物件い訪れ定期的に換気や通水を行わなければなりません。
しかしながら、賃貸に出せば借主が換気や通水といったことを日常的に行ってくれるため、所有者による管理が不要となります。
2-3.維持費の負担感が軽くなる
マンションは所有しているだけで固定資産税や損害保険料、管理費、修繕積立金といった維持費が発生します。
マンションには戸建てにはない管理費や修繕積立金という維持費も加わるため、戸建てよりも維持費の負担感は重いです。
賃貸に出せば、一般的には家賃収入が維持費を上回るため、維持費の負担感を軽くすることができます。
2-4.節税できる場合がある
不動産を賃貸に出して赤字が発生した場合、損益通算という仕組みによって所得税を節税できます。
仮に赤字になってしまったとしても、その赤字を所得税の節税に利用できるため、上手くいかなかったときでも一定のメリットを享受できます。
2-5.将来的な資産価値を維持しやすい
建物を賃貸に出すと、借主が自然と建物の管理をしてくれます。
また、寿命により設備が壊れた場合には、貸主の負担で修繕しなければならないため、設備も正常に作動する状態を維持できます。
建物を常に適切な状態とすることができることから、売却をいつでも選択しやすく、資産価値を維持しやすいです。
関連記事:自宅を賃貸に出すメリット・デメリット14選!必要な費用・税金や具体的な手順も解説
3.相続したマンションを賃貸に出すデメリット
賃貸に出す場合でも、一定のデメリットは存在します。
この章では、相続したマンションを賃貸に出すデメリットについて解説します。
3-1.物件によっては高額なリフォームが必要となる
相続したマンションを賃貸に出す際のデメリットは、物件の状況によっては高額なリフォームが必要となるケースがあることです。
特に築年数の古いマンションでは、ユニットバスを交換しないと賃貸に出すには厳しい場合もあり、150~200万円程度の費用が生じることもあります。
売却なら所有権が買主に移ることから、買主が購入後に自由にリフォームできるため、築年数の古い物件でもリフォームせずに売ることは可能です。
しかしながら、賃貸は所有権が借主に移らず、借主が自由にリフォームできないため、貸主がリフォームをしなければなりません。

竹内英二【資格】不動産鑑定士、賃貸不動産経営管理士
【ワンポイントアドバイス】
リフォームが必要か否かは、賃料査定を依頼して管理会社に判断してもらうことが適切です。不要なケースも多いですし、仮に必要でも最低限必要な箇所を教えてもらえるため、費用を最小に抑えることができます。
実際にどの程度のリフォームが必要かは、現地を見なければ正確に判断できません。訪問査定なら物件の状態をプロが直接確認し、“リフォーム不要で貸せるか”も含めて具体的にアドバイスしてもらえます。
3-2.空室が長引くと維持費の負担が重くなる
賃貸は都合よく常に借主が決まるとは限らないため、空室が長引くと維持費の負担感が重くなる点がデメリットです。
売却すれば維持費の負担から解放され、空室が長期化したときに維持費の負担に悩むこともなくなります。
3-3.確定申告の手間が発生する
賃貸に出して不動産所得が年間で20万円を超えると、毎年、確定申告が必要となってきます。
不動産所得とは、不動産を賃貸に出したときに得られる所得のことであり、家賃収入から必要経費を差し引いた利益のことです。
| 不動産所得 = 収入金額 - 必要経費 |
単純に家賃収入だけでなく、固定資産税や損害保険料等の必要経費を差し引く必要があります。
知識のない方は初年度の確定申告は大変ですが、慣れれば楽にできるようになります。
最初のうちは、基礎知識や申告方法等を色々調べなければならない点がデメリットです。
3-4.管理の手間・トラブル対応の負担がかかる
マンションを賃貸に出せば、一定の管理の手間やトラブル対応の負担が生じる点がデメリットです。
例えば、手間としては、借主が退去した後に貸主がハウスクリーニングや修繕を実施しなければならない場合があります。
トラブルとしては、家賃の不払いや借主が騒音等で隣接住戸に迷惑をかける等が考えられます。
ただし、これらの手間やトラブルは管理会社に管理を委託しておけば、管理会社が適切な処置を行ってくれるため、貸主側の対応を最小限に抑えることができます。
関連記事:マンションを貸す7つのデメリットは?売却や空き家のまま放置と比較
4.相続したマンションの売却と賃貸の判断基準

この章では、売却と賃貸のどちらを選ぶべきかの判断基準について解説します。
| 状況 | 売却が適しているケース | 費用が適しているケース |
|---|---|---|
| 現金の必要性 | 税金が払えず、すぐに現金が必要 | 急いで現金化する必要なし |
| リフォーム費用 | 捻出できない | 不要、又は少額の費用で済む |
| 判断に迷う場合 | / | 賃貸(後から売却も可能) |
4-1.すぐに現金が必要なら売却
まとまった現金がすぐに必要な場合には、売却が適しています。
例えば、相続では相続税の納税のために現金が必要な場合もあります。
相続税の納税と申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
相続税の納税のために現金が必要な人は、すぐに売却する必要があります。
4-2.リフォーム費用が捻出できなければ売却
築年数が古い物件の場合、多額のリフォーム費用が必要となることもあります。
リフォーム費用が捻出できなければ売却するということも、合理的な判断です。
まずは売却査定を依頼し、どれくらいのリフォームをしなければならないか把握してから判断することをおすすめします。
この時、注意したいのがリフォーム業者に査定を依頼しないことです。
理由は売却する上で必要ない箇所までリフォームする高額な見積もりになる可能性があるからです。
売却する上で必要最低限な箇所はどこか、売却を依頼する不動産会社に確認し余計な箇所までリフォームをしないようにしましょう。
関連記事:リフォームなしで家を貸すにはどうしたらいい?方法と判断基準を解説
4-3.貸せる物件でどちらか迷うならとりあえず賃貸
前節の2つの理由には該当せず、売却か賃貸で迷ったら賃貸に出すのがおすすめです。
賃貸に出しても、後から売却は可能なので急ぎで現金化する必要がなければ家賃収入を得ながら資産を活用できます。
特段、急いで売る必要がないのであれば、活用して家賃収入を得ておく方がお得です。

竹内英二【資格】不動産鑑定士、賃貸不動産経営管理士
【ワンポイントアドバイス】
売却はいつでもできるため、本当にお金が必要となったときに実施すれば良いといえます。投資を伴わずに資産運用ができることは相当なメリットがあるため、そのメリットを十分に享受して頂ければと思います。
5.相続したマンションを賃貸に出す手順

相続したマンションを賃貸に出す手順は次の通りになります。それぞれ詳しく解説します。
- 家財道具を処分(処分業者に依頼、貴重品は事前に整理)
- 賃料査定を依頼(複数の管理会社に依頼、無料で可能)
- 管理を委託(管理委託契約を締結、手数料は家賃の約5~10%)
- 入居者を募集(管理会社が広告・審査を実施)
- 賃貸借契約を締結(重要事項説明後、契約書を確認)
5-1.家財道具を処分する
相続したマンションを貸したり売ったりするためには、まず家財道具を処分することが必要です。
家財道具の処分は、費用はかかりますが荷物処分業者に依頼すれば一気に処分することはできます。
ただし、荷物処分業者に依頼する場合でも、故人の形見や貴金属、仏壇等は事前に選別して運び出しておくことは必要です。
荷物処分業者は金額が異なるため、依頼する前は複数の荷物処分業者に相見積を取り、実績等も踏まえて適切な業者を見つけることが望ましいといえます。
5-2.賃料査定を依頼する
賃貸に出すには、管理会社(不動産会社)に賃料査定を依頼します。
賃料査定では、そもそも貸せるのか、また貸せるとしたらいくらで貸せるかを知ることができます。
「そのまま貸せる」または「このままでは貸せない」といったことも判断してもらえるため、賃貸に出すにはまずは査定を依頼することが必要です。
管理会社に依頼する賃料査定は、無料となります。
高く貸してくれる会社やサービスの充実した会社を見つけるためにも、賃料査定は複数の管理会社に依頼することが望ましいです。
特に訪問査定を依頼すれば、建物の状態や周辺環境まで加味した“実勢に近い賃料”を提示してもらえます。机上の査定より精度が高いため、今後の判断材料として大きな差が出ます。
また、賃料査定は家財道具の処分前に行っても問題はありません。
5-3.管理を委託する
賃料査定の結果、管理を委託したい会社が見つかったら、管理の契約を締結します。
管理会社は、入居者募集だけでなく、借主からのクレーム対応や家賃の入出金管理、家賃滞納の督促等を行ってくれる会社です。
賃貸経営の成否を分ける重要な役割を担うため、実績が豊富でサービスの充実した会社を選ぶことが望ましいといえます。
管理会社に対して支払う管理委託手数料は、家賃の5~10%程度が相場です。
管理委託手数料は、毎月の家賃から差し引かれる形となり、空室時は生じない費用となります。
また、管理委託料は借主が決まらない限り発生しないため、管理委託契約を締結しただけでは費用が発生することもないです。

竹内英二【資格】不動産鑑定士、賃貸不動産経営管理士
【ワンポイントアドバイス】
管理会社は実績が豊富なだけでなく、サービスのIT化が進んでいる会社も選ぶ際のポイントです。オンライン内見や電子契約に対応している会社は遠方の入居希望者も獲得しやすいため、借主が決まりやすくなります。
5-4.入居者を募集する
管理会社に管理を委託すると、管理会社は早速に入居者募集を開始します。
入居者募集に関しては、全て管理会社が行ってくれるため、貸主には実質的に手間は発生しません。
適切な借主かどうかを判断する入居審査も、管理会社が実施することが通常です。
5-5.賃貸借契約を締結する
入居審査を経て適切な借主が見つかったら、管理会社は契約締結の前に借主に対して重要事項説明を行います。
借主が重要事項説明の内容に納得すれば、賃貸借契約の締結に進むというのが流れです。
賃貸借契約書の書面は、管理会社が用意してくれます。
通常は管理会社から事前に賃貸借契約書を提示されるため、貸主も賃貸借契約書の内容を確認しておくことが望ましいです。
関連記事:分譲マンションを賃貸に出す方法を徹底解説!手順から注意点・費用・税金まで知っておきたい知識
6.相続したマンションを賃貸に出すときの5つの注意点

この章では、相続したマンションを賃貸に出すときの注意点について解説します。
6-1.相続人が複数いる場合は合意形成する
マンションを複数の相続人による共有で相続した場合、賃貸に出すには原則として全員の同意を得ておくことが望ましいです。
仮に賃貸後に借主とトラブルが発生した場合、共有者の賃貸人に多大な負担が発生する恐れがあります。
共有者全員が事前に賃貸に同意をしていればトラブルが生じても全員で解決しようとする心理が働くため、共有者間で揉めにくくなります。
6-2.管理規約の賃貸制限条項を確認しておう
分譲マンションでは、管理規約で賃貸に関する一定の制約事項が設けられていることが一般的です。
具体的には、賃貸借契約書の中に借主に対して分譲マンションの管理規約および使用細則に従わせることを条文に盛り込まなければならない等の制限があります。
また、借主に対して管理規約および使用細則を遵守させる誓約書の提出を求められるケースも存在します。
賃貸に出す前は、管理規約の中で賃貸に関する部分を確認することが必要です。

竹内英二【資格】不動産鑑定士、賃貸不動産経営管理士
【ワンポイントアドバイス】
賃貸借契約書には、借主が分譲マンションの管理規約および使用細則に規定する義務に違反した場合には、賃貸借契約を解除できると記載しておくことも適切です。
6-3.原状の写真を撮っておく
相続したマンションは、既に一定の汚れや損傷を抱えていることが通常です。
賃貸に出すと借主が退去した際に、汚れや損傷がもともと存在していたものなのか、それとも借主が生じさせたものなのかで揉めてしまうことがあります。
退去時に揉めないようにするには、貸す前の原状を写真等でしっかりと記録しておくことが必要です。
関連記事:マンションを貸す際の注意点とは?流れや費用など賃貸管理会社が基礎知識を徹底解説
7.よくある質問

この章では、相続したマンションを賃貸に出す際によくある質問について解説します。
7-1.相続したばかりでも賃貸に出せますか?
リフォーム等が不要であれば、相続したばかりでも賃貸に出せます。
むしろ空き家のままにしておくと維持費が生じることから、準備が整い次第賃貸に出すことが望ましいです。
7-2.誰の名義で賃貸契約を結べばいいですか?
物件を引き継いだ相続人、つまり新たな所有者の名義で賃貸借契約を締結します。
借主に対して所有者が誰かを明確にするためにも、名義変更(相続登記)の後に賃貸借契約を締結することが望ましいです。
7-3.築古マンションでも賃貸需要はありますか?
立地が良ければ築年数が古くても、賃貸需要は十分に存在します。
逆に築浅物件であっても、立地が極端に悪ければ、貸しにくいです。
7-4.管理会社の選び方のポイントは?
相続物件はファミリータイプが多いため、ファミリータイプの管理に実績があり、かつ、1戸からでも管理を引き受けてくれる管理会社が適切です。
例えば、戸建て賃貸や転勤時に貸す賃貸等の管理実績がある管理会社は、1戸のファミリータイプの管理に慣れていることから、管理を任せやすいといえます。
まとめ:相続マンションは賃貸も選択肢に!まずは査定で価値を把握しよう
以上、相続したマンションを賃貸に出すというテーマについて解説してきました。
マンションは戸建てに比べると立地の良い物件が多いことから、総じて賃貸に適しています。
賃貸に出すメリットは安定した家賃収入を得られるという点であり、デメリットは物件によっては高額なリフォームが必要となるという点です。
賃貸に出せるか否かは自分で判断するのではなく、まずは賃料査定を依頼してプロの意見を聞くことが重要です。
相続したマンションでも賃料査定は無料で依頼できることから、売るか貸すかを迷っている段階でも構いません。まずは相続したマンションが“いくらで貸せるのか”を知ることから始めましょう。
本当に貸せるのか、貸すとしたらいくらなのか――それを正しく知るには訪問査定が一番確実です。
専門スタッフが現地で物件の状態をチェックし、最適な活用方法までご提案します。お気軽に相談して頂ければと思います。
この記事の執筆者
カテゴリ: マンションを貸す 関連記事
賃貸に役立つコラム記事
海外赴任時の賃貸に関して
転勤時の賃貸に関して
一戸建て・マンションの賃貸に関して
査定に関して

人気記事TOP5