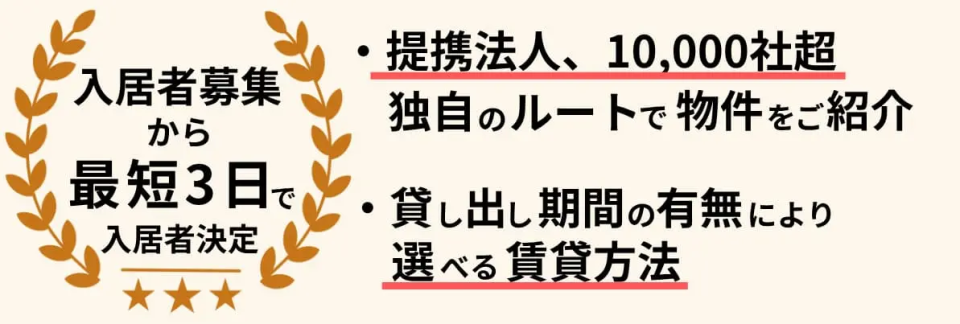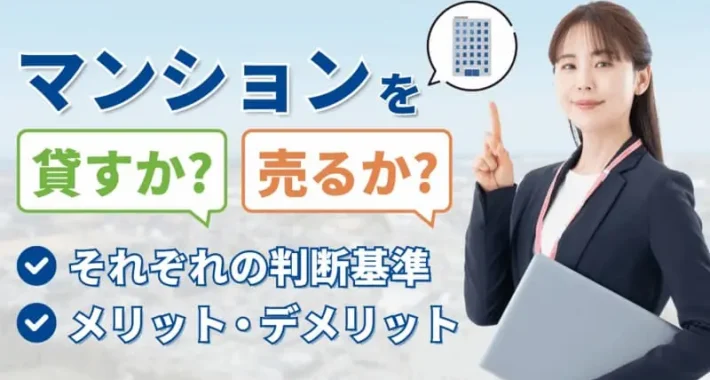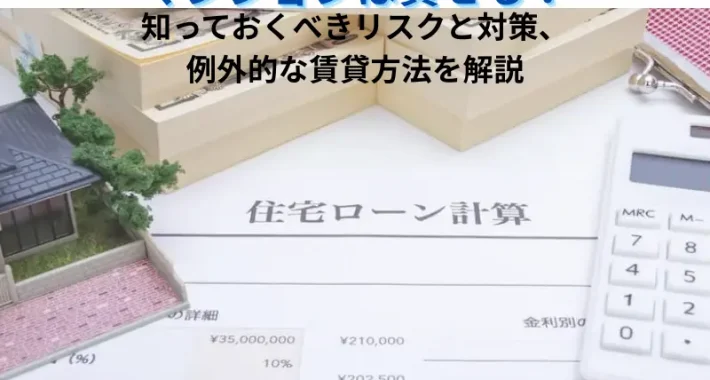転勤などの理由により一時的に使っていないマンションを所有している場合、入居希望者を見つけて貸し出すことで家賃収入を得られます。ただ、家賃収入を得ることで、納める税金が増えてしまうのではないかと不安を感じている人もいるでしょう。
後述しますが、マンションを貸した際の節税ポイントの一つは「費用をできるだけ経費として計上すること」です。他にもいくつかの節税ポイントはありますのでこの記事では、マンションを貸すことで増える可能性がある税金や節税のコツを紹介します。所有している不動産を有効活用して収入を増やしたい方は、ぜひチェックしてください。
目次
1. マンションを貸す際にかかる税金

マンションを貸す際にかかる税金は、いくつか種類があります。以下でどのような税金があるのか確認しておきましょう。
| 税金 | 概要 |
|---|---|
| 所得税 | 個人の所得に対して課される税金。マンションを貸した場合は、家賃などの収入から必要経費を差し引いた金額に対して課される。 |
| 復興特別所得税 | 東日本大震災の復興のための財源に充てるため、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に、通常の所得税に上乗せして徴収される特別税。 |
| 住民税 | 地方税の一種で、都道府県が課税する道府県民税と、市区町村が課税する市町村民税の総称。教育、福祉、ゴミ処理など、地方自治体が提供する公共サービスをまかなうために使われる。 |
| 個人事業税 | 個人事業主が都道府県に対して納める地方税のひとつ。個人で事業を行う際、さまざまな行政サービスを利用していることから、その経費の一部を負担するための税金となる。賃貸事業の規模が大きい場合に対象となる。 |
| 税金 | 概要 |
|---|---|
| 固定資産税 | 土地や家屋の所有者に対して課される地方税。固定資産の所有者は、その資産価値に応じて算定された税額を、固定資産の所在する市町村に納める。マンションを貸していても、所有者はオーナーであるため、固定資産税は入居者ではなく所有者に請求される。 |
| 都市計画税 | 都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために、市町村が課税する地方税。市街化区域内にある土地や家屋の所有者に課される。 |
上記のようにマンションを所有するだけでもかかる税金もあれば、貸すことでかかる税金もあります。家賃などの収入によって税率が変わるものや、マンションの価値によって変わるものなど様々であるため、基本的には毎年その時の情報をベースに計算して算出する必要があります。
後ほど出てくる「所得税」の部分では、マンションを貸した際の収入によって最も変動する可能性が高い所得税が、実際にどのくらいかかる可能性があるのかを解説します。600、700万円でのモデルケースがありますので、参考にしてみてください。
2. マンションを貸すと税金は増える?
マンションを貸すと、家賃によって収入が増えるため課される税金は増えます。
前提として、家賃収入から経費を差し引いた所得に応じた税金が課されます。どのくらい税金が課されるかについては、家賃をいくらに設定するかで変わってきます。経費の額を故意に増やすことは難しく、本末転倒となってしまいます。そのため、事前に税金のシミュレーションをしたい場合にはどのくらいの家賃を想定すべきか算出することが大切です。
家賃の設定は立地や物件状態に合わせて決めます。マンションを貸す上で、費用と収入のバランスは税金にも影響するため、家賃設定は重要です。家賃の目安は、賃貸管理会社に賃料査定を依頼することで概算の金額を把握できます。詳細の家賃は持ち家であるマンションに訪問後、その場で提示されます。賃料査定を依頼すると、あわせて賃貸管理のプロから早く高く成約できる提案などが受けられます。
当社ではどちらも無料です。まずは一度、賃料査定と合わせて貸す際の税金のことなども相談してはいかがでしょうか。
3. マンションを貸すと増額になる可能性のある税金と税率

マンションを貸して得た家賃収入は不動産所得です。所得金額が増えるため、所得税や住民税などが増えてしまう可能性があります。
所得金額は収入から経費を差し引いた金額で、経費が収入を上回ると赤字となります。
ここでは、増額になる可能性がある税金の計算方法や税率について確認しておきましょう。
【増額になる可能性のある税金】
3-1. 所得税
所得税は累進課税という課税方式をとっており、家賃収入による所得が増えるほど税率が上がって、課される税金の額が多くなります。以下の表を参考にしていただけるとよくわかりますが、税率は一律ではなく増えるごとに大きくなり、所得が4千万円を超えれば45%もの税率が課されてしまいます。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円〜 | 45% | 4,796,000円 |
表にある通り控除額もありますので、5%から10%の段階に変わっても、実際に支払う所得税額は急に2倍にはなりません。
たとえば、課税される所得金額が600万円の場合、所得税額は以下のように計算します。
所得税額 = 所得金額 × 税率 – 控除額
所得税額 = 6,000,000円 × 0.20 – 427,500円 = 772,500円
仮に、家賃収入を得ることで、課税される所得金額が700万円に増えたと想定すると、所得税額は以下のように計算されます。
所得税額 = 7,000,000円 × 0.23 – 636,000円 = 974,000円
所得金額が100万円増えたことにより、所得税を約20万円多く納付する必要がありますが、税率と控除額が変わったことによる増額分は1,500円しかありません。
所得金額に対する税率は法律で決まっているため、個人ではどうしようもありません。しかし、経費として計上する額が大きければ、所得額を減らすことが可能です。この点については後ほど解説しますが、節税ポイントをうまく活用すれば負担額を減らせる可能性があるので、節税できるかどうかを確認して効率よく資産を形成していきましょう。
3-2. 復興特別所得税
復興特別所得税は、2011年の東日本大震災からの復興を目的として創設され、2037年まで徴収されます。すべての納税者が対象であり、税額は所得税額の2.1%です。
所得金額ではなく、「所得税額」の2.1%であることがポイントです。「所得税額」が少なくなるほど、復興特別所得税の納税額も少なく済みます。同様に課税される所得金額が600万円の場合と、700万円の場合で比較してみましょう。
600万円の場合の所得税額は772,500円でした。よって、復興特別所得税は次のように計算されます。
復興特別所得税 = 772,500円(所得税額) × 0.021 = 16,222円
課税される所得金額が700万円の場合の所得税額は974,000円でしたので、復興特別所得税は以下のとおりです。
復興特別所得税 = 974,000円(所得税額) × 0.021 = 20,454円
所得金額が100万円増えたことで、復興特別所得税は約4,000円増額となったことがわかります。所得税ほどの負担はありませんが、復興特別所得税も所得が増えることで負担が大きくなる税金の一つなので覚えておきましょう。
3-3. 住民税
住民税も所得金額をもとに計算されるため、家賃収入を得ることで基本的には増額となります。住民税は次のように計算されます。
住民税 = 所得割 + 均等割
均等割は、都道府県民税1,500円と市区町村民税3,500円の合計であるため、所得金額に関わらず一定です。所得割の額が所得に比例して高くなります。
所得割は、所得金額から、基礎控除・社会保険料控除・医療費控除などの所得控除を差し引いた「課税所得金額」の10%から、住宅ローン控除などの税額控除をさらに差し引いて求めます。
所得割 = 課税所得金額 × 0.10(税率10%) – 税額控除
所得金額が増えて、課税所得金額が増えるほど所得割の金額も大きくなるため、結果として住民税も高くなってしまいます。
4. マンションを貸すときの4つの節税ポイント

マンションを貸して収支を良くしようとする場合、適正な賃料を得ることや、賃料収入のない空室の期間を短くすることは重要です。しかしそれだけでなく、費用をできるだけ経費として計上したり、青色申告の特別控除を利用したりすることによって、節税を行うこともまた、収支の改善へとつながります。
ここでは、節税の4つのポイントを紹介しますので、ぜひチェックしてください。
4-1. 費用をできるだけ経費として計上する
所得税や住民税は、課税所得金額を減らすことで節税できます。課税所得金額は、収入から必要経費や各種控除を差し引いて求めるため、可能なかぎり経費として計上することが節税のポイントといえるでしょう。
経費として計上できるのは、マンションを貸すことに関する費用のみです。たとえば、次のような費用を経費として計上できます。
- 固定資産税
- 減価償却費
- 火災保険料や地震保険料などの損害保険料
- リフォーム費用やクリーニング費用
- 賃貸管理会社へ支払う手数料
固定資産税や損害保険料といった継続的に支払う費用はもちろん、壁紙やフローリングのリフォーム費用やクリーニング費用など、貸し出す前の準備段階でかかった費用も経費として計上できます。各費用については「不動産所得を算出する際に経費として認められる費用」で詳しく解説します。
意外と多くの費用が経費となりますが、当然のこととして、プライベートの食費や交通費などは経費として計上できません。故意でなくても、経費になるものとならないものの違いを理解せずに、本来経費として申告できないものを経費として申告すると、税務署の調査が入ったり、税金を追加で徴収されたりする恐れもあります。
初めて経費に加えようとするような費用で理解が曖昧なものについては、そのまま申告するとより面倒なことになってしまう場合もあるので、事前に国税庁のWEBサイト「タックスアンサー」(No.2210 やさしい必要経費の知識)などで調べたり、税務署や国税局電話相談センターに問い合わせたりして確認しておくなどの注意が必要です。
4-2. 減価償却費を計上する
減価償却費は、固定資産(マンション)の購入費を耐用年数で分割し、毎年計上できる帳簿上の費用です。購入した年の次年度以降、耐用年数で分割した購入費用を経費として計上していくこととなるため、長期間にわたって所得税と住民税の負担を抑えられます。
ただし、購入費の全額を初年度に全て計上することはできません。マンションの購入費用は必ず減価償却費として計上することを覚えておきましょう。
4-3. 青色申告の特別控除を利用する
確定申告時の際に簡単に行える白色申告ではなく、少し難しくて手間がかかる青色申告をすることも大きな節税ポイントです。青色申告を行うことで最大65万円の青色申告特別控除が受けられるため、課税所得金額を大きく減らせます。結果として、所得税や住民税を節税できるのです。
青色申告を行うためには、事前に税務署に開業届や青色申告承認申請書を提出しておかなければなりません。そのうえで、毎年、確定申告の期間内に必要な書類を提出する必要があります。
確定申告には難しそうなイメージもありますが、誰でも簡単に使える会計ソフトなども販売され、電子申告に対応しているものもあります。税理士に相談すれば、しっかりと経費になるものを洗い出してもらえて、有益なアドバイスなどももらえるかも知れません。
しかし、その分費用もかかりますので、依頼をするかどうかは「依頼することによって節税できそうな額がどれくらいになりそうか」で判断することが大切です。家賃などの収入とそこにかかる税金が高額になりそうなときには、利用することで収支を改善できるかも知れません。そうでなければ、まずは申告の仕方の概要や便利そうなソフトの価格なども調べてみて、自力で節税できないかチャレンジしてみるのもおすすめです。
青色申告には青色申告特別控除のほかにも、節税に有効ないくつもの特典がついているので、できる限り活用していくべきです。また、青色申告以外にも社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など、一般的に適用される控除などもあるので、これらをなるべく多く活用することで、税負担を最大限抑えることができます。
参考:
「No.2070 青色申告制度」[国税庁]
「確定申告書等作成コーナー」[国税庁]
4-4. 他の副業による赤字と合算する
所得税額は、給与所得や不動産所得、雑所得などを合算した金額をもとに決定されます。本業による給料や、マンションを貸すことによる家賃収入だけでなく、その他に副業をしている場合は、その収入も合計されるのです。
副業に関する所得を計算する際も費用を経費として計上することで、節税の効果が得られます。副業が黒字の場合、全体の収入が増えるため所得税額も上がりますが、逆に経費が多くかかって赤字となっている場合は他の所得から赤字分を差し引くことができ、所得税は下がります。
行っている事業について、利益が出ているものは申告の義務がありますが、収支がマイナスの事業についても経費がかかったことを申告することで節税になります。
5. 不動産所得を算出する際に経費として認められる費用
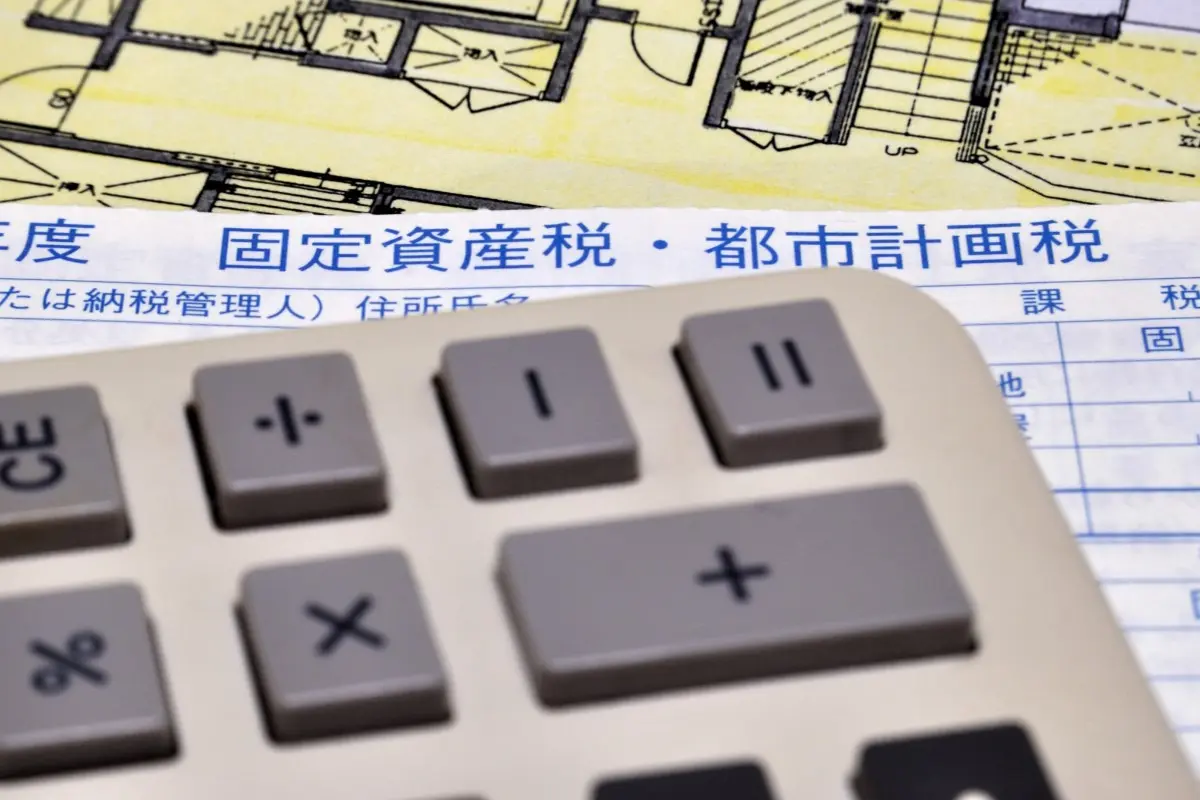
不動産所得は、不動産収入から経費を差し引いて求めます。不動産所得が増えるほど、より多くの税金を納める必要があるため、節税を狙ううえでは、さまざまな費用をできるだけ経費として計上することが大切です。ここでは、マンションを貸す際に経費として認められる費用を紹介します。税金対策において損をしないよう、ぜひチェックしておきましょう。
【不動産所得を算出する際に経費として認められる費用】
5-1. 固定資産税
固定資産税は、土地や建物などの不動産を所有している人が納税すべき税金です。マンションの一室を所有している場合も例外ではありません。固定資産税の額は、以下のような計算式で求められます。
固定資産税額 = 固定資産評価額 × 税率
固定資産評価額とは、自治体によって決められる不動産の価値のことで、購入価格ではありません。この評価額は、3年ごとに見直されます。税率は自治体ごとに異なりますが、標準税率の1.4%を採用している地域がほとんどです。
たとえば、固定資産評価額が1,000万円、税率が1.4%の場合、固定資産税額は以下のように計算できます。
固定資産税額 = 1,000万円 × 0.014 = 14万円
固定資産税額は、比較的大きな額の経費であるため、しっかりと計上して節税しましょう。
5-2. 都市計画税
都市計画税は、各自治体の都市計画に関する事業を行うために徴収される税金です。原則として、都市計画区域のうち「市街化調整区域」を除く区域に所在する土地や家屋に課されます。「市街化調整区域」内であっても条例により課税対象となる場合があります。固定資産税と同様、土地や建物などの所有者に納税義務があります。都市計画税額は、次のように計算されます。
都市計画税額 = 固定資産評価額 × 税率
都市計画税額は、固定資産税と同様に、固定資産評価額をもとに計算します。税率は0.3%以下を基準として設定され、自治体によって異なる場合もあるため注意しましょう。たとえば、固定資産評価額が1,000万円、税率が0.3%の場合、都市計画税額は以下のように計算できます。
都市計画税額 = 1,000万円 × 0.003 = 3万円
マンションを貸している場合でも毎年納税する必要があるため、忘れずに経費として計上しましょう。
5-3. 損害保険料
火災保険料や地震保険料といった損害保険料も経費として計上できます。マンションを所有している場合、損害保険に加入しているケースも多いでしょう。火災保険については、自宅として使用している場合は経費になりませんが、マンションを貸す場合は、不動産収入を得るために必要な経費として認められます。
一方で地震保険料控除については、給与所得のみでも控除の対象となるため、マンションを貸し出す前から契約しているものも控除の対象として計上できます。
5-4. 減価償却費
減価償却とは、事業のための建物などを購入したとき、その費用を数年間にわたって分割して経費とすることです。マンションを購入した場合も減価償却の考え方が適用されるため、購入した年に、購入費用全額を経費とすることはできません。マンションの構造や中古・新築ごとに耐用年数が定められており、その年数に分けて、減価償却費として計上します。
仮に、マンションの購入費用を3,000万円、耐用年数を47年とすると、減価償却費は以下のように計算できます。
減価償却費 = 3,000万円 ÷ 47年 = 63.8万円
減価償却費は、会計上の経費であるため、実際の支出とは異なります。減価償却の仕組みを利用することで、長期間にわたって経費として計上できます。節税にもつながりますので、しっかりと理解しておきましょう。
5-5. マンションの管理費
マンションの管理組合や、マンション管理の委託先の管理会社へ支払われる、マンションの管理費・修繕積立金も経費として計上できます。
もし自分でマンションの管理をする場合は、移動のための交通費やガソリン代、駐車場代や高速道路の料金、掃除道具を購入するための費用など実費を経費にできます。
5-6. 賃貸管理手数料
マンションを貸す際は、賃貸運用の管理を賃貸管理会社へ委託するケースも多いでしょう。管理委託料や手数料、入居者募集のための広告費などは経費として認められます。
5-7. リフォーム費やハウスクリーニング費
マンションを貸す前に、壁紙を貼り替えたり、キッチン設備を入れ替えたりする場合もあるでしょう。ハウスクリーニングを行ってから、入居してもらうことも一般的です。このようなリフォーム費用やハウスクリーニング費用も経費として計上できます。
5-8. 賃貸管理会社の担当者との打ち合わせ費用
マンションを貸す場合に、賃貸管理会社などの業者の担当者と打ち合わせが必要となったとき、この打ち合わせを行うために費用が発生したような場合は、その分も経費として認められます。
1回分は少ない額でも複数回にわたると大きな費用になることもあります。自分で払った飲食代や交通費などがあれば、領収書は保管しておき、それらも経費とすることで、節税効果が高まるでしょう。
5-9. 経費として認められない費用もあるため注意が必要
ここまで紹介したように、できるだけ多くの費用を経費とすることで節税効果は高まりますが、経費として認められないものもあるため注意が必要です。当然のこととして、不動産事業の経費として認められる範囲は、不動産事業のためにかかった費用に限られます。なので、プライベートの飲食費や交通費などは、もちろん経費にはなりません。
また、これも当たり前だと思われる方がいらっしゃるかも知れませんが、所得税や住民税も経費として計上できません。住宅ローンがある場合には、利息は経費にできますが、元本は経費ではないため注意しましょう。前述の通り、マンション購入にかかった費用であれば、減価償却費として計上できます。
【経費として認められない費用(一例)】
- 個人的な食事で支払った食費
- 土地や建物を手放すときにかかる費用
- 所得材や住民税など個人的に支払う税金
経費として認められる範囲を超えて申告すると、税務署の調査が入り、ペナルティを受ける可能性もあります。過少申告加算税や重加算税が課せられ、本来の税額に追加して税金を納めることになる可能性もあるため、十分に注意しましょう。
関連記事
リロケーションで得た収入の確定申告はどうする?

6. マンションを貸したときに不動産収入に含まれるもの

所得は所得税法によって10種類に分類されており、土地やマンション、一戸建てなどの不動産を貸すことによるものは、不動産所得に分類されます。
具体的には家賃や礼金などを不動産収入として計上し、経費を差し引いたうえで不動産所得を求めなければなりません。ここでは、どのようなものが不動産収入に含まれるのかを解説しますので、申告漏れにならないようチェックしておきましょう。
【マンションを貸したときに不動産収入に含まれるもの】
6-1. 家賃
家賃はマンションを貸す際のメインの収入といえるでしょう。部屋の大きさや築年数、立地やリフォーム状況などによって家賃相場は異なりますが、たとえば月15万円に設定すれば、年間180万円もの家賃収入を確保できます。この家賃収入は不動産収入として申告が必要です。
6-2. 駐車場賃料
マンションの一室だけではなく、駐車場を一緒に貸すケースもあるでしょう。駐車場の賃料は、家賃に含める場合もありますし、別に徴収する場合もあります。どちらにしても駐車場の賃料は不動産収入ですので、家賃と同様に申告しなければなりません。
6-3. 共益費や管理費
共益費や管理費は、マンションの共用部分の設備を維持管理するための費用です。具体的には、エレベーターの点検費用、共用部分の照明の電気代、廊下や階段の清掃費用などとして使われます。家賃とは別に、共益費や管理費を徴収する場合も不動産収入として計上しましょう。
6-4. 礼金
礼金とは、マンションなどの不動産を貸したことに対する謝礼として、入居者に支払ってもらうお金です。敷金とは異なり、礼金は入居者に返却する必要はありません。
地域や慣習によって名称は異なり、「敷引き」などと呼ばれるケースもあります。礼金は、家賃の1〜2ヵ月分とするのが一般的ですが、「礼金なし」とすることも可能です。
返還しないので、これも不動産収入です。
6-5. 契約更新料
契約更新料は、賃貸契約を更新するための手数料や謝礼として、入居者に支払ってもらうお金です。契約期間はさまざまですが、1〜2年ごとの契約更新に合わせて支払ってもらうのが一般的です。契約更新料も不動産収入ですので、確実に計上しておきましょう。
このとき、退去時、全部または一部を返還するような敷金・保証金などは、返還しない分だけを不動産収入として加算するようにしましょう。
以上、マンションを貸したときに不動産収入に含まれる主なものを紹介しました。ここで紹介したもの以外にも、部屋を貸すことによる収入がある場合は、不動産収入として計上します。
7. マンションを貸す際の税金に関するよくある質問
Q1. 家賃収入はいくらまで非課税になる?
給与所得、公的年金等の雑所得がある人の場合、家賃収入から必要経費を差し引いた額が20万円未満なら確定申告の提出が不要です。そのため、家賃収入に対する所得税がかかりません。
また、家賃収入がメインの所得である場合には、家賃収入から必要経費を差し引いた額が基礎控除額の48万円以下なら確定申告が不要です。この場合も、家賃収入に対する所得税がかかりません。
関連記事
家賃収入で確定申告が必要なケースと適した確定申告の方法とは

Q2. 家賃収入は手取りでどれくらい残る?
家賃収入における手取りは、家賃の額やかかる経費に左右されます。加えて給与所得がある場合は、給与所得と合算した所得金額に対しての税率になるので、さらに複雑化します。
経費については、物件によっては修繕が必要となる場合もありますし、リノベーションなど規模によっては何百万円とかかることも想定されるでしょう。
手取りでどのくらい残るかを知りたい場合は、賃貸管理会社に査定を依頼することで、想定賃料と貸すために必要な修繕を教えてもらうことができます。事前にシミュレーションを行うことで、かかる経費と収入のバランスを見極め、効率的な賃貸運営に近づくことができるでしょう。
関連記事
マンションの賃貸で収益を増やすコツを紹介!

関連記事
マンションを賃貸に出すと手取りはいくら?家賃収入の利益計算を解説

Q3. 家を貸す相手によって税金は変わる?
家を貸す相手によって税金が変わることはありません。あくまでも自身にいくらの収入が入るかを基準に税金は決まるため、相手がだれかという点は税金の額に影響を与えることは無いです。
ただし、1以上の海外赴任中に法人へ賃貸を行った場合、賃料の20.42%が源泉徴収されます。納税管理人を通じて確定申告を行うことで、払いすぎた税金の還付を受けることができます。
関連記事
海外赴任中にマンションを貸した場合の確定申告

友達や知り合いに無償で貸し出す場合には、金銭のやり取りが無いので所得によって発生する所得税などは発生しません。いずれにせよ、基本は所得の額に応じて税金が変わるので、知り合いに貸してもその額が変動するようなことはありません。
Q4. マンションを貸すと増えるかもしれない税金は?
マンションを貸すと、以下の税金が増える可能性があります。
- 所得税・復興特別所得税
- 住民税
詳しくは「マンションを貸すと増額になる可能性のある税金」でご確認ください。
Q5. マンションを貸すときの4つの節税ポイントとは?
マンションを貸すときの4つの節税ポイントは以下の4つです。
- 費用をできるだけ経費として計上する
- 減価償却費を計上する
- 青色申告の特別控除を利用する
- 他の副業による赤字と合算する
詳しくは「マンションを貸すときの4つの節税ポイント」でご確認ください。
Q6. マンションを貸したときに含まれる収入には何がある?
マンションを貸したときに含まれる収入はこちらです。
- 家賃
- 駐車場賃料
- 共益費・管理費
- 礼金
- 契約更新料
このとき、退去時、全部または一部を返還するような敷金・保証金などは、返還しない分だけを不動産収入として加算するようにしましょう。
詳しくは「マンションを貸したときに不動産収入に含まれるもの」でご確認ください。
Q7. 不動産所得を算出する際に経費として認められる費用とは?
マンションを貸す際に経費として認められる費用を紹介します。税金対策において損をしないよう、ぜひチェックしておきましょう。
- 固定資産税
固定資産税額 = 固定資産評価額 × 税率
税率は自治体ごとに異なりますが、標準税率である1.4%を採用している地域が多いです。 - 都市計画税
都市計画税額 = 固定資産評価額 × 税率
※税率は0.3%以下を基準として設定され、自治体によって異なる場合もあります。 - 損害保険料
- 減価償却費
- 賃貸管理手数料
- マンションの管理費
- リフォーム費やハウスクリーニング費
- 賃貸管理会社の担当者との打ち合わせ費用
経費として認められない費用もあるため注意が必要です。
詳しくは「不動産所得を算出する際に経費として認められる費用」でご確認ください。
Q8. 節税するためには何が重要?
節税するためには、マンションを貸すことに関わる費用をできるだけ経費として計上することが重要です。固定資産税や都市計画税、マンションの管理費用やハウスクリーニング費用など、さまざまな費用が経費として認められます。
詳しくは「マンションを貸すときの4つの節税ポイント」でご確認ください。
Q9. マンションを貸すのは本当に儲かる?
マンションを貸すことによって必ずしも儲かるわけではありません。赤字になることも想定されます。
しかし、給与所得などの他の所得がある場合は、この赤字分を所得から差し引くことができ、節税に繋げることができます。不動産所得における経費には、実際には支払うことのない「減価償却費」が含まれているため、帳簿上赤字となっていても、実際の収支は黒字という場合もあります。
家賃収入と基本的な経費をベースに儲かるかどうかを確認したい場合には、まず査定をしてみることをおすすめします。査定をして実際にどのくらいの家賃収入が見込めるのかを確認し、そこから収益シミュレーションをしてみましょう。その結果、自身の物件で本当に儲けることができるのかどうか、ある程度予測を立てることが可能です。
関連記事
マンションを貸して本当に儲かる?失敗しない全知識と収支シミュレーションを徹底解説

8. 【まとめ】マンションを貸すと税金が増える可能性もある!うまく節税することが重要
今回は、マンションを貸すと増額になる可能性のある税金や、節税のポイントについて解説しました。所得税や住民税などは、所得金額によって増減するため、家賃収入を得ることで増える可能性があります。
不動産収入を維持したままでも、不動産所得を減らすことができれば納税額は少なく抑えられます。領収書など、普段から保存しておかなければならない書類もあります。経費になる項目を把握しておきましょう。
こうした基本的な知識を身に付けた上で、節税のための対策を講じてマンションを貸し出すことができれば、そこには大きな利益を生み出すチャンスがあります。しばらく空けている家がある方も、転勤などで一時的に使わなくなってしまうマンションがある方も、ぜひ一度貸し出すことを検討してみましょう。
参考
「所得税の税率」[国税庁]
「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」[国税庁]
「不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」[国税庁]
この記事の編集者
カテゴリ: マンションを貸す 関連記事
賃貸に役立つコラム記事
海外赴任時の賃貸に関して
転勤時の賃貸に関して
一戸建て・マンションの賃貸に関して
査定に関して

人気記事TOP5