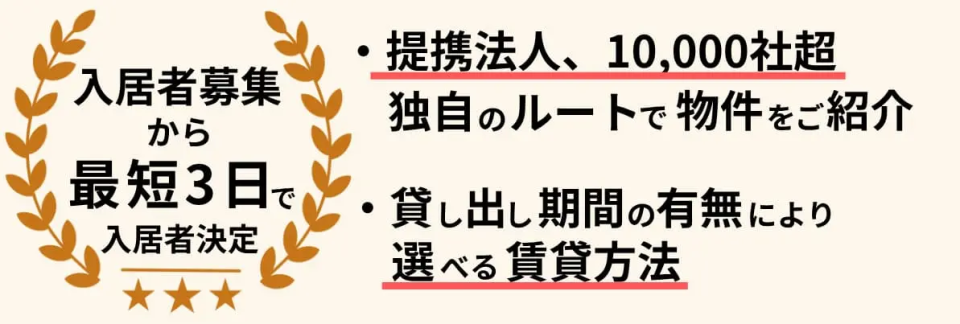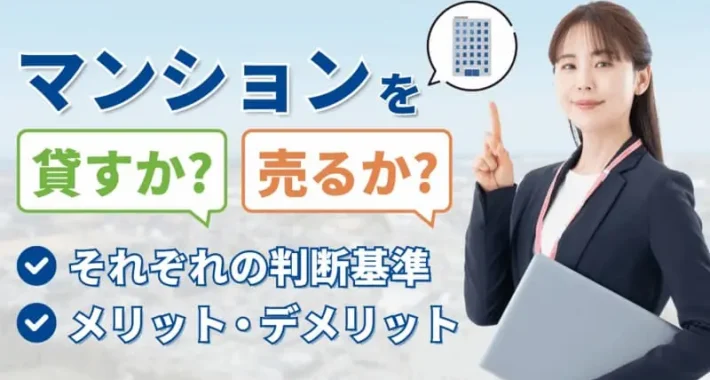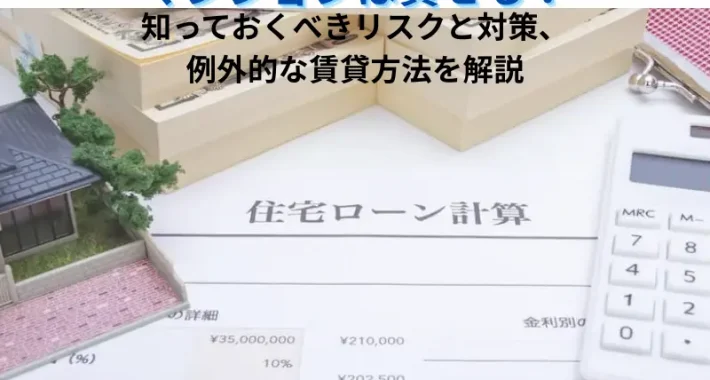分譲マンションを上手に貸すためのコツ│貸し出す方法や注意点、必要な費用を解説
分譲マンションを活用する方法の一つとしてマンションを貸し出すことには様々なメリットが考えられます。しかし、実際に貸す際の手順や注意点、必要な費用などについて詳しく知らないという方も多いでしょう。
分譲マンションを貸すにあたっては、予め理解しておくと役に立つことや、リスクを抑えるためのコツなどがあります。この記事では、これらについてご案内します。分譲マンションを持っている方、分譲マンションを貸すことを考えている方は必読です。ぜひ最後までご覧ください。
1. 分譲マンションを貸すメリット

分譲マンションを貸す大きなメリットは、安定的な家賃収入を得られる点ですが、それだけではありません。分譲マンションを貸すことは、他にもメリットがあります。
1-1. 家賃収入を得られる
分譲マンションを貸すことの最も大きなメリットは、毎月一定の金額を家賃収入として得られることでしょう。分譲マンションは、交通の利便性や充実した共用設備、セキュリティの高さといった付加価値によって、収益性の高い家賃収入を得ることができます。
貸主が賃貸管理会社を利用する場合、管理手数料が必要となりますが、賃貸管理の手間をほとんどかけずに家賃収入が得られるようになります。
賃貸契約中であれば、原則として毎月家賃収入を得られます。家賃が変動することはめったになく、毎月一定額が支払われるため、賃貸契約中は数年単位での収入が見込めます。
現金収入であることから生活費に組み込みやすく、株式投資などと比較して安定性が高いといえます。
転勤によって自宅を離れている場合には、赴任先でかかる居住費や生活費の支えになり、本業とは別の収入確保につながります。
1-2. 資産として保有し続けられる
今後、居住地域の地価が上がる見込みがあるならば、分譲マンションを資産として保持し、価値が高まったときに売却することで、多くの利益をもたらす可能性があります。そのタイミングが来るまでは、いったん賃貸をしながら検討する時間を作れることもメリットです。
1-3. 再度、住むことができる
転勤で一時的に自宅マンションを離れはするものの、将来的には戻ってくる予定や将来譲渡する可能性、愛着があれば、賃貸がおすすめです。売却をすれば、再度住むことはできなくなります。住む所は確保しておいた方が先々に何かあった際に困らないかもしれないという思いがあるならマンションを貸すことで将来の選択肢が増えることもメリットでしょう。
1-4. マンションの価値を維持できる
空き家にしておくと通風、通水が行われず家は傷んでいきます。貸して生活してもらうことで通風や通水などのメンテナンスが自然と行われ、空き家にしておくよりも劣化が防げます。マンションは資産です。物件の状態が良ければ資産価値の維持に直結します。
貸すことは、資産を保有しながら同時に劣化も防げるのでメリットになります。
2. 分譲マンションを貸すデメリット
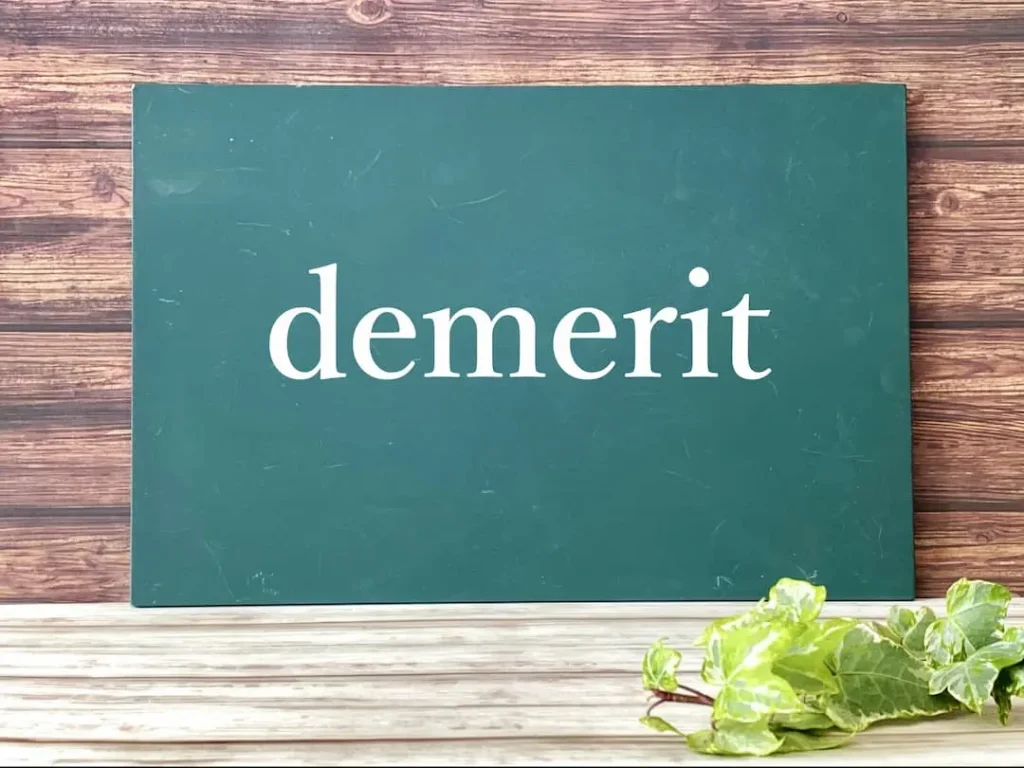
分譲マンションを貸すことで、家賃収入が得られることや資産を維持できるなどのメリットがあります。一方で、分譲マンションを貸すことによって発生するデメリットとしては次のようなことが考えられます。
2-1. 家賃収入を上回る費用が発生すると赤字になる
分譲マンションを貸す場合、修繕積立金や所得税といった必然的にかかってしまう費用、基本的にはかける必要性のあるハウスクリーニングなどの費用、収入を増やす目的であえてかけるリフォームの費用などがあります。
収入が費用を上回れば問題ありませんが、これらの費用の中には入居者が決まり、賃料が得られるよりも前に発生するものもあります。
そのため、空室が発生すると、費用の回収が遅れ場合によってはなかなかうまく利益につながらない可能性、つまりは収益に関するリスクがデメリットとして存在します。
空室リスクがデメリットとして挙げられるのは、賃貸のためにかけた手間や費用が無駄になるからです。
このときの費用としては次のようなものが挙げられます。
なお、管理委託料は管理会社に物件などの管理を委託せず、貸主自ら管理を行う場合は発生しませんが、こちらでは費用として説明しています。管理業務は多岐に渡ることから貸主が管理業務全般を行うのは手間がかかるため、管理会社に委託することをおすすめします。
仲介手数料
入居者が見つかり賃貸契約を結べた際に不動産会社に支払う報酬で成功報酬です。家賃の1ヶ月+消費税が上限となっています。
ただし、入居者の了承があれば入居者に仲介手数料を全額負担して貰い、貸主は仲介手数料を払わない場合もあります。
管理委託料
マンションを貸した際、物件、入居者の管理を委託した場合に発生します。
マンションの管理業務は多岐に渡りますが、中には自主管理といって貸主が全て対応する管理方法もあります。しかし、本業が会社員で何かの都合でマンションを貸すことになり、知識も経験もない場合は管理業務を委託する方が予期せぬ手間を軽減できるのでおすすめです。管理委託料の相場は家賃に対して5~15%程度です。
マンション管理費・修繕積立金
マンションを貸しても所有者は貸主から変更されるわけではないため、これらの費用は引き続き支払う必要があります。
ハウスクリーニング、設備の修繕費
マンションを貸すのが初めての場合、エアコン、ガス給湯器、フローリングなどの状態を確認し、入居者が快適に生活できるよう必要な修繕をしなければいけません。
また、初めて貸す場合は貸主の費用負担でハウスクリーニングをします。入居者が決まれば、特約でハウスクリーニング費用を負担して貰うこともできます。内容は経年劣化による壁紙の張替えや水回りの清掃などで、貸主個人では難しいため専門業者に依頼します。
入居中、借主の故意・過失により傷などをつけてしまった場合、国土交通省のガイドラインではつけてしまった傷を直すためにかかる費用の相当額を請求できると明示されています。
参考:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について[国土交通省]
税金
固定資産税
マンションの所有者が1月1日時点で所有しているマンション(資産)の価値に応じて、マンションの所在地の市区町村に納めます。自分が住まずに貸している場合でも納税しなければいけません。
都市計画税
固定資産税と同様に1月1日時点で都市計画区域内にある土地や家屋に対して課される税金です。固定資産税と併せて納税するので同じように感じるかもしれませんが、税率や対象が異なります。
所得税・住民税
マンションを貸して得られた家賃収入は不動産所得になります。会社員の場合は不動産所得に加えて給与所得があります。2つの所得を合算すると所得が増え、この増えた所得に所得税、住民税が課税されるので、納税額が増え、課税された分が支出が増えます。
2-2. 管理に手間がかかる
マンションを貸す場合、家賃回収、滞納時の対応、退去時の細かい敷金精算など、多岐に渡る管理業務があります。
そうした管理業務のほとんどは手数料を支払い賃貸管理会社に委託することが可能ですが、その場合は賃貸管理会社に問い合わせることや、委託を申し込むための手続きが必要となります。
また、必要かどうかは状況によりますが、確定申告や、住宅ローンに関する銀行への相談も分譲マンションを貸すために発生する手間として考えられます。
3. 分譲マンションを貸す手順

次に、分譲マンションを貸す場合の手順についてお伝えします。
3-1. 賃貸管理会社(または不動産仲介会社)を探す
分譲マンションを貸す場合、まずは賃貸管理会社を探しましょう。管理業務は主に入居者募集などを始めとした仲介業務、賃貸中の物件や入居者管理を行う入居者管理に分かれます。
仲介業務
入居者募集、内見時の対応、賃貸借契約
賃貸管理業務
家賃回収・送金、設備故障時等の入居者対応、家賃滞納時の督促業務、退去時の原状回復、敷金精算
管理会社に管理業務を委託する賃貸管理サービスを利用するには手数料が掛かりますが、賃貸を始めるときにはそうしたサービスを利用することをおすすめします。突発的な設備の故障への対応は自ら行うのが難しい場合も考えられます。家賃滞納などのトラブルを解決したり、未然に防いだりするためには法的な知識が必要となることもあります。管理業務を管理会社に委託することで、分譲マンションを貸すことによる業務の負担も、運用上のリスクも小さくすることができます。
仲介と管理業務の両方を委託できる賃貸管理会社(または管理業務も一部行う不動産仲介会社)もあるので、そのような不動産会社を探した方がより手間を軽減できます。
管理会社の選び方について、詳しくは「5. 分譲マンションを貸すときのコツ」で後述しますが、初めてマンションを貸し出すような場合、賃貸管理会社をいくつか見つけたら、数社に問い合わせてみることで、各社の業務範囲や手数料を確認してみることをおすすめします。そうすることで、各社のサービスに共通することや違いが分かり、賃貸の基本的な進め方を理解できるとともに、自分にあったサービスを見つけやすくなります。
転勤のためなどで一定期間だけマンションを貸し出すのであれば、賃貸管理会社の中でも特にリロケーションを専門に取り扱っているリロケーション会社が有力な候補になります。シチュエーションに応じて、相談する会社を見極めましょう。
3-2. 貸し出す方法を決める
賃貸管理会社が決まったら貸し出す方法を決めましょう。貸し出し方法に次の3つがあります。
普通借家契約
普通借家契約普通借家契約は、賃貸における一般的な契約方法です。入居者の希望があれば、契約を更新して住み続けることができます。一般的には2年ごとに更新があり、貸主からの解約には正当事由が必要であり、一方的な解約は難しくなっています。長期的に貸し出すのに最適です。
定期借家契約
定期借家契約は、契約時に設定した契約期間のみを賃貸期間とする契約方法です。原則として、入居者は契約期間満了までに退去しなければなりませんが、貸主と入居者の双方が合意することで、賃貸期間を延長するために改めて契約することは可能です。
普通借家契約と比べて、解約について貸主にとって有利となる条件が付された契約方法となるため、家賃は相場の8割程度に抑えるなど、他の条件を緩める必要性が生じることは、定期借家契約のデメリットです。
予め期限を定めてから貸し出せるので、将来的に家を使う予定がある場合にはおすすめの契約方法で、定期借家契約は6ヶ月前までに告知することで解約が可能になります。
一時使用賃貸借契約
一時使用賃貸借契約は、持ち家を一時的に賃貸として貸し出したい場合に用いられる契約方法です。たとえば転勤などで、数年の期間だけ賃貸に出す場合が該当します。この契約では、一時使用の事由が存続する期間が契約期間となります。
また、一時使用賃貸借契約は、契約時に定めた契約期間は遵守しなければいけませんが、3ヶ月前までに告知すれば解約可能です。そのため、定期借家契約よりも期間の柔軟性が高い契約方法です。ただし、入居者の立場が不安定となるため、2年以上の賃貸保証期間を設定して貸し出すことが一般的です。
期間を限定した契約であるため、普通借家契約と比較して借主が見つかりにくく、賃料を低めに設定する傾向にある点はデメリットとして挙げられます。
【一時使用賃貸借契約がおすすめの人の特徴】
- 転勤など、一時的に家を貸し出したい人
- 転勤や建替え工事など期間が変更になる可能性が高い
関連記事
家を貸す時の契約方法の注意点

3-3. 募集条件を決める
マンションの借主を募集する際には、以下で挙げたような契約の条件を事前に決定します。
- 家賃
- 契約の種類
- 契約期間
- 敷金・礼金
- 保証人
- 保険
この際のポイントは、「どのような内容だと借り手がつきやすいのか」ということです。
たとえば、賃料を高めに設定すれば、確かに収入は増えるかもしれません。しかし、周辺の相場より割高の場合に入居者は見つけづらくなり、空室が続いてしまうリスクも高くなります。
募集の条件を設定するときには、希望する条件を無制限に詰め込むのではなく、他の物件の情報も参考にするなどして、借り手がつきやすい条件のことも考えながら、賃貸管理会社の担当者と一緒に決めていきましょう。
3-4. 入居者を募集する
賃貸マンションの入居者募集から内見対応までを実際に行うのは、賃貸管理会社と不動産仲介会社の仕事です。必ずしも貸主が直接対応する必要はありません。
ただし、入居希望者が内見に来た際に好印象を持ってもらうためには、室内の整理整頓・清掃が重要です。入居希望者が訪れるのに先立って、事前のメンテナンスをしっかりと行っておきましょう。
室内の設備が古くなっているのであれば、状況に応じてリフォームなども検討しましょう。リフォームの内容によっては費用以上の収入につながる場合もあります。
3-5. 入居審査を経て賃貸借契約を結ぶ
入居希望者から申し込みが入ったら、入居審査を実施します。また、入居希望者が募集条件とは異なる条件を希望する場合は、条件交渉も行われます。
入居審査は保証会社や賃貸管理会社独自の基準により行われ、職業、収入、過去の家賃滞納歴などの支払い能力が審査対象です。そして、最終的な入居の可否は貸主が決めます。
入居審査に問題がなく、契約条件においても貸主と入居希望者双方の合意が得られたら、賃貸借契約を締結します。
エントランスや廊下など共有部分の使い方や騒音に関する注意事項など、マンションの細則も賃貸管理会社が伝えますが、生活している中で気付いた設備の使い方などあれば、管理会社に伝えて合わせて入居者に伝えてもらいましょう。
4. 分譲マンションを貸すときの注意点

実際に分譲マンションを貸すとき、特に注意したい点として、管理方法と節税対策が挙げられます。
住宅ローンを利用しているならば、事前の銀行への相談も怠ってはいけません。
今後、その分譲マンションについて、再度貸主自身が自宅への入居を予定しているならば、そのためにどんな契約方法が適しているかも検討しておくとよいでしょう。
4-1. 住宅ローンを利用していれば金融機関へ確認
住宅ローンの残債がある状態でマンションを第三者に貸すことは、金融機関との契約において違反になりえます。一般的に住宅ローンの融資条件には、「居住用の家を買う」という項目があるためです。つまり、住宅ローンは自分が住む家のためにしか適用されないのです。
住宅ローンの支払いが残っているマンションを賃貸するのであれば、基本的に事業用ローンへの組み換えが必要になります。この場合、住宅ローンよりも金利が高くなり支出が増えるので注意が必要です。
ただし、転勤期間中の一時的な賃貸といったケースでは、金融機関に相談することで住宅ローンの使用を認めてもらえる場合も少なくありません。まずは一度、相談してみましょう。
4-2. 住宅ローン控除は受けられない
住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)は、住宅ローンを用いて住宅を購入する際に使える制度です、節税効果が非常に大きく、控除の対象となる物件を購入する人の多くが利用している制度です。
しかし、ローンを組んだ人(もしくはその家族)が住宅ローンを使って購入した家に住んでいない場合、住宅ローン控除を受けることはできません。転勤から戻ってきて再度その家に入居した場合は、事前に手続きをしておくことで残りの期間分の控除を受けられる場合がありますが、その場合は帰任後すぐに控除は受けられず再入居の翌年から再開できます。
住宅ローン控除はあくまでも第三者へマンションを貸している年度中は控除が受けられなくなると覚えておきましょう。
4-3. 自分がいずれ住むのなら契約内容に注意
分譲マンションの賃貸が一時的なものであり、最終的に自分が居住する予定なのであれば、賃貸契約の内容に注意してください。
不動産の賃貸借契約で広く一般的に用いられている「普通借家契約」は、解約の条件において他の賃貸借契約よりも借主に有利となる賃貸借契約です。
契約期間満了を迎えたときは、借主が望む限り契約を更新することが原則となっており、住まいを明け渡してほしい場合はそのための正当事由が求められます。この正当事由というのは抽象的なものではありますが、ただ「自分が住みたくなったから」「転勤が終了したから」といった理由での解約は認められません。
貸主の一存で部屋を空けてもらうことはできず、いざ自分が入居しようと思っても、その時に都合よく自宅が空くとは限らないため、自分が特定の時期を迎えたときに居住する予定があるならば、あまり合っていない契約方法と考えられます。
転勤などの理由から一時的にマンションを貸すのであれば、一時使用賃貸借契約や定期借家契約を用いたリロケーションがおすすめです。
4-4. 禁止事項を決めておく
マンションを貸す際には前もって禁止事項を決めておきましょう。
具体的な例として「ペットの飼育」「タバコの喫煙」などが挙げられます。これらを認めた場合に、臭いの付着、ひっかき傷、壁紙等の変色が考えられます。それらの変化が清掃や修繕では元通りにできない程度であったときに、資産価値を損なう恐れがあるため、築年数が浅い物件などでは特に、可否に慎重になるべき事項となります。
一方で、これらは入居者に認めることによって、募集の門戸を拡げられる事項でもあります。入居者が決まりやすくなることや、賃料を高めに設定しやすくなるというメリットがあります。
資産の価値を守ることは大切です。しかし、条件の設定を厳しくし過ぎると入居者が見つかりにくくなります。築年数や室内の状況を加味し、賃貸管理会社と相談して禁止事項を決めましょう。
4-5. 入居前と退去時の物件の状態を確認する
分譲マンションを貸し出す前に室内の状態を動画や写真などで記録しておきましょう。退去時に存在する損傷が入居者によるものならば「原状回復」のための費用として支払いを請求できるからです。入居前の家の状態を写真等で記録し、退去時の状態と比較することで、解約時の請求が適切であると主張でき、トラブルを減らすことができるでしょう。
これらは賃貸管理を委託する際に管理会社に相談しておくと良いでしょう。
5. 分譲マンションを貸すときのコツ

分譲マンションを貸すときの手順は「3. 分譲マンションを貸す手順」で前述した通りですが、その中でも賃貸を成功させる上で特に重要なこととして、賃貸を始める前に行う賃貸管理会社選びがあります。
賃貸を賃貸管理会社なしで始めることもできますが、発生する様々な業務を個人でこなすのは、賃貸運営をしたことがない人にとって骨が折れます。そのため、多くの場合で、賃貸を始めるにあたり最初に行うことは、賃貸で業務を任せる賃貸管理会社を選定することからとなります。
そこで、賃貸管理会社である当社が考える、選定で失敗しないコツについて、最後に触れておこうと思います。
最も重要なことは「いかにして各社サービスの差異を理解し、自分の行いたい賃貸に合ったサービスを間違えることなく見つけるか」ということです。
サービス選びにおいて、「違い」とその意味を見極めるための知識を身に着け、注意を払っていくことこそが、賃貸におけるコツだと言えます。
そのために意識しておきたい具体的なポイントをいくつか挙げてみましょう。
5-1. 最初は大手を含む数社から話を聞く
良いサービスを見つける上で、複数社から話を聞いておくことは有効です。話を聞く社数が増えるほど、その後の整理には時間も手間もかかってしまうので、そのことは負担となりますが、それでも2~3社は話を聞いてみることをおすすめします。そうすることで、各社を相対的に見比べる視点が得られます。
また、このときに、高い専門性を持っていそうな大手の会社を探して候補に含めておくと良いでしょう。そうした会社は、取り扱い件数に期待できます。そのため、様々なケースに応じられるように、サービスの種類が豊富であることを期待できます。
サービスの説明を複数社から聞いていく中で、その中に大手が一社以上存在することで、情報収集を効率的に進めていくことができます。どこか大手の話を基準に持つことで、その後の比較検討の見通しも良くなります。2社目以降の話では、それ以前に聞いた話が各社サービスを評価する上でのヒントになります。
5-2. 各社の違いに着目する
複数社からサービスの説明を聞いていると、その中には共通して説明されることが必ず存在します。賃貸管理サービスを選ぶには、まず賃貸管理サービスがどういうものであるかを理解しなければならないため、そうした共通点を把握することも重要ではありますが、それ以上に重要なことは、各社各サービスの「違い」を見逃さないことです。
基本的な違いとなりやすい点としては、何かの業務を「行う」、「行わない」といったサービス提供範囲や、リスクに対する保証範囲の違いと、それらに応じた費用の差異があります。
説明の中で、気になったサービスや保証に関する話はメモに控えておくなどして、他社の話を聞く際に、同様のサービスが提供されるかどうかを聞いてみるなどすると良いでしょう。
「安価である分サービスの提供範囲は狭く、手間が残ってリスクも高い」「手数料はかかるがリスクが低く、手間もほとんどかからない」などの違いから、自身における優先順位を考えて、希望する賃貸運営に合ったものを選ぶことが重要です。
5-3. 賃料査定額は妥当性が大事
賃貸管理会社に問い合わせる最初のきっかけとして多いものは、分譲マンションを貸し出したときにいくらの賃料が期待できるかを調べてもらえる、無料の賃料査定です。
このときに、最初に出される査定額は、限られた情報から概算であることが多いですが、より大切なのは「実際にはいくらくらいで入居者募集を始めていくのが妥当か」ということです。
これは、金額を「高く提示する会社が良い」ということでも「安く提示する会社が良い」ということでもありません。適正とされる範囲を示し、状況に応じた提案(高め・安め)があることが大切です。設定する賃料の範囲に関する根拠や、提案の理由について話を聞いて、合理的で納得できるものであるかを考えなければなりません。
ある社の査定額について、他社と金額に差があった場合、そのことについて見解を求めることも有効で考え方の違いを確認できます。
6. まとめ
ローン中の家を売るには、ローンを完済している必要があります。ローンを完済しないと抵当権を抹消できないため、家を売ることはできません。そのため、ローン中の家を売る際はオーバーローンなのかどうかを確認する必要があります。
オーバーローンの場合は、不足分を自己資金で補填するか、住み替えローンを利用して借り換えるか、任意売却を検討しなければいけません。また、任意売却は完済できなくても抵当権を抹消できますが、残ったローンは引き続き返済しなければいけない点に注意してください。
転勤が理由で家を売るか検討している場合は、賃貸も視野に入れてみましょう。賃貸に出すことで持ち家を売ることなく所有し続けられますし、家賃収入の設定額次第ではローンの負担なく家を残すことが可能です。
この記事の編集者
カテゴリ: マンションを貸す 関連記事
賃貸に役立つコラム記事
海外赴任時の賃貸に関して
転勤時の賃貸に関して
一戸建て・マンションの賃貸に関して
査定に関して

人気記事TOP5